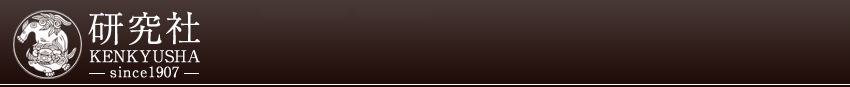

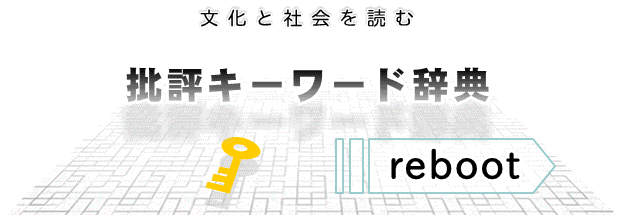
第5回
 | シェア |
 |
「シェア」と「コミュニティ」 |
みんなで分かち持つこと。独り占めせずに、できるだけ多くの人のアクセスを可能にし、みんなが使用できるようにすること … 。「シェア」ということばが持つそういった意味合いには抗しがたい魅力がある。シェアハウスに限らず相互的なシェアで結ばれた人間関係には、何か豊かで良好なコミュニティのイメージすら想起させるものがある。もちろん濃密なコミュニティにあこがれを抱くというのは、「田舎」を理想化したうえでそこにノスタルジックな願望を投影するという、都会暮らしの絵に描いたような手すさびでもある。この点はわたしのような「都会」暮らしにとっては否定しがたいものではあるが、それにしてもその魅力に抗うのはいつも難しいと感じる。だがそれだけだろうか。現代を生きるわたしたちにとっては何か普遍的とも言えそうな強い魅力が「シェア」にはいつもあるようにも思われるが、それに加えて今まさに「シェア」の持つイメージはその輝きを増しているようにも思われる。いまわたしたちの多くが抱えているしんどさや生きづらさを幾分かでも和らげてくれるものとして、「シェア」は魅力を増してはいないだろうか?
私有財産の廃止を国是とし、すべてを国有(共有)とするソ連の国家社会主義が崩れてからこれまでの約30年は、私有化の歴史でもあった。ソ連に限らず日本でも、国営企業も業界団体の既得権益もその多くが民営化の流れに抗することはできなかった。新自由主義と呼ばれる一連の政治的判断は日本では70年代末あるいは80年代初頭から加速し続け、今に至る。一般的に使われる「民営化」が privatization の訳語であることを考えれば、これは私有化あるいは私企業化であったともいえる。ここまで私有化を進めてきたうえで、共有するという意味を持つ「シェア」がいまになって改めてもてはやされるというのは少し奇妙とも感じられるかもしれない。端的に、「シェア」は民営化=私有化を進める新自由主義に逆行しているように(少なくとも表面的には)見えるのだ。
だが、ここにもう一つの私有化を加えてみたらどうだろう。すなわち、社会的責任とそれに伴う不安の民営化=私有化だ。一般的な意味での民営化と軌を一にして、緊縮政策と呼ばれる社会保障や福祉関連費の切り下げが行われてきた。これはもちろん医療費負担の増加などのように単純に社会的責任を個人の経済的負担に転嫁するものであるわけだが、同時にこれは、そういった一連の施策による将来への不安を個人に負わせるものでもあった。端的に、社会保障費削減や雇用の流動化が相まった人びとの暮らしの不安定化もまた、公的な保障ではなく個人のもの、つまり個人が有する責任だとされてきたのだった。現在の日本のあちらこちらで散見される自己責任論は、少なくともその一部は、社会的責任の民営化=私有化の効果として位置付けることができる。こういった広く新自由主義と呼ばれる一連の政策は、緊縮経済とセットになって将来への不安や生きづらさまでも私有化させてきたのだ。こういった中だからこそ、「シェア」が身にまとう様々なイメージは一層魅力を増しているのだろう。ある「シェア」に関する著作の中では「今社会が直面しているほとんどの問題は、「シェア」という概念を取り入れることによって解決することができると確信を持つようになりました」(石山アンジュ『シェアライフ』 133)とまで語られる。
考えてみれば、「シェア」の放つ魅力はこういった社会不安への処方箋というイメージにとどまるものではないのかもしれない。ツイッターのリツイート機能(他人のツイートを自分のアカウントからもそのまま再ツイートして拡散すること)は情報のシェア(共有)だと言えるし、そもそもフェイスブックにはその名のとおりシェア機能が備わっている。ネット上のコミュニティの基盤となっているものも「シェア」なのであり、SNS の普及率が伸び続けていることを考えても、「シェア」は私たちの生活の一部になっていると言えるだろう。
「シェア」の魅力をいくつかのレベルで見てきたがここまでくれば、この語の持つ魅力の淵源がはっきりする。そう、それは「コミュニティ」の希求だ。共有すること、分かち持つこと、そして経験や思想を共有するという意味で共感すること。これらがすべて人と人との深い関係に基づいたコミュニティにつながるものなのだ。そういった意味では、シェアハウスも「今社会が直面しているほとんどの問題」への処方箋としての「シェア」も SNS 上での「シェア」も、同じ願望をそれこそ「シェア」しているのであり、それがいまひときわ注目を集めているように見えるのは、社会的不安や責任をシェアできなくなってきたという時代状況に負うところが大きいと思われる。そしてだからこそ、これは重要なことなのでここではっきりと確認しておきたいのだが、この願望は切実でもあるし真正なものだ。多くの人たちが必要だと感じ、あるいは失われつつあると感じているからこそ、その願望が広く共有されている。このこと自体、軽んじられるべきではない。そういった意味では「シェア」を求めるのは別に新しいことではない。それでもやはり昨今の「シェア」の隆盛を見る限りでは、何か新しいものというイメージもあるのは確かだ。ではその新しさとは何なのだろうか。
 |
シェアリングエコノミーと、「新しさ」の凡庸さについて |
いま注目を集めている「シェア」に関する議論はそのほとんどが実はシェアリングエコノミーに関するものだ。前掲の石山はこれに「共感型経済」とルビをふって、それを「つながり資産」を形成するものと位置付けている。シェアリングエコノミーは単なるモノとモノのやり取りを超えて、経済活動に人間的なつながりを取り戻すものであり、それが共感をベースとした「つながり資産」となり個人を孤独から救うというロジックだ。私有を目的とするのではなく消費あるいは使用を通じて共感を豊かにするもの、それがシェアリングエコノミーの新しさ、ということになる。
この点に加えてもう一つ見ておくべき「新しさ」がある。それを端的に表したのが、2010年という早い段階で「シェア」について語ったレイチェル・ボッツマンとルー・ロジャースのその名も『シェア』で語られた以下の一文だろう。ボッツマンとロジャースは「シェア」を中心とした新しい動きを協働型消費(collaborative consumption)と呼び次のように述べている。
おそらく、協働型消費のいちばんおもしろい点は、イデオロギーに縛られず、社会主義と資本主義の両極端な期待を同時に満たすことができるところだ。凝り固まった思想は必要ない。もちろん、システムに限界はある。とりわけ、個人が所有権や自己の裁量を手放さない、または手放せない場合はそうだ。だが、こうしたかたくなさも、いずれは変わってゆくだろう。(25-26)
要するにシェアとは、イデオロギーの有無にかかわりなく、私有を目標とせず共有を軸にした効率的使用を目指すという意味で社会主義的であり、それでも利潤を上げ続けるという意味で同時に資本主義的でもある、というわけだ。石山が共感と呼んだものはここではより双方向的かつ主体的な響きを持つ協働という語で表現されている。そのどちらも、所有を消費の主軸に据えないという点を強調している。これに加えて本書では、協働型消費が大量生産大量消費の代替案であり環境負荷を大幅に軽減できるという点が繰り返し述べられる。終わりなき所有欲の充足に対応した大量生産大量消費へのある種のカウンターとして、シェアリングエコノミーの可能性が強調されているのだ。
これらシェアリングエコノミーのもたらすとされる効果の内実については、とりわけ「新しさ」の真偽については後述するとして、ここでは両者に見られるこの「新しさ」を強調するという身振りそのものの意味を確認しておきたい。
石山およびボッツマンとロジャースの論じ方から思い出すべき「新しさ」についての、あるいは根本的な変化についての議論は、アメリカの社会学者ダニエル・ベルの『イデオロギーの終焉』(1960)だろう。ベルは、科学技術の発展が大量生産を可能にし、それにより社会全体が経済的発展を遂げつつあるという点で東西両陣営の社会状況が似通ってきていると述べ、そういった中でイデオロギーは社会全体を動員してあるべき方向へ引っ張っていく力を失ったのだ、と喝破した。もちろん、ベルは東西冷戦のさ中にソ連とアメリカが同じ政治体制になったと述べたわけではないし、貧困が撲滅されたなどと主張しているわけでもない。政治的な問題を論じる知識人の間で「福祉国家や脱中心化された権力、混合経済と政治的多元性システムを受け入れるというおおまかなコンセンサスが存在」(Bell 402-403)しているとし、旧来のイデオロギー闘争が社会変革を駆動する力をなくしたと分析しているのだ。ベルの議論の正当性についてはあまり深追いできないが、ここでは福祉国家と混合経済の有用性が強調され、一般的な意味での豊かな社会が到来しているという認識を確認するにとどめておこう。
だがそのわずか二年後にマイケル・ハリントンがはっきりと示したように、福祉国家成立とテクノロジーによる生産性向上で豊かになっているはずのアメリカには、不可視な形で4千万から5千万人もの貧困にあえぐ「もう一つのアメリカ」が存在していた。
もう一つのアメリカの住人たちは、社会のその他の人びとに生活水準の向上をもたらしてきたまさしく発明と機械そのものの犠牲者だ。この住人たちは経済のなかでさかさまになっており、そういった人びとにとってより高い生産性というのは往々にしてより条件の悪い仕事を意味した。(Harrington 12)
ハリントンの指摘は辛辣だ。もしハリントンの言うとおり、豊かな社会が貧困層を取りこぼしただけでなくむしろその豊かになる過程そのものがもう一つのアメリカと呼ばれるほどの大規模かつ不可視化された貧困層を生み出したのだとなれば、社会の発展と進歩を自明の前提とする議論は成立しなくなってしまう。たとえ理論的には混合経済が行き過ぎた資本主義を計画に則って進めることで抑制し、福祉国家が文字どおり福祉を国家の重要な役割と規定しているのだとしても、その実、それらが多くの貧困層を取りこぼし、さらには不可視化することで状況を悪化させているのだとするなら、その有用性には看過しがたい問題があると言わざるを得ないのだ。
どうやら大局的な視点で宣言される「終わり」や根本的な変化は、何かを見過ごすことで、あるいは見ないようにすることでなされ得るものらしい。そして、若干先走って結論めいたことを言ってしまうと、それはここで取り上げたい「シェアリングエコノミー」についても言えることなのではないだろうか。もちろんこれは終わりではなく何か根本的な変化の始まりを告げるものとして喧伝されているという意味で、ちがったものに思えるかもしれない。だが一般的に言って、終わりの感覚とはこれまでとはちがったものの始まりを不可避なものとして見出す感覚と表裏一体となった断絶の感覚にほかならない。だが変化とは断絶と連続の複雑で長期的な混淆であるはずだ。すでに何度か言及している石山アンジュは、実は内閣官房 IT 総合戦略室長の指名する「シェアリングエコノミー伝道師」の一人なのだが、彼女は次のように高らかと宣言している。
そして、今日、この「シェア」という考えそのものが、消費スタイルの変化だけでなく、経済のあり方、社会のあり方、そして私たちの生き方そのものを変えようとしています。(石山 21)
この華々しい新時代幕開け宣言は、内閣官房とシェアリングエコノミーのベンチャー企業代表たちで構成された「シェアリングエコノミー協会」の、要するに利害関係者の公式見解と言えるものだ。この楽観的とすら言える変化宣言を見ると、やはりハリントンの教訓を思い起こさずにはいられない。ここでの変化は、進歩は、何を不可視化しているのだろうか。このありふれた「新しさ」はこれまでも繰り返されてきたよくある「新しさ」の喧伝なのだから取るに足らないとも言えるだろう。しかしだからこそ、この自身の立場から見える「新しさ」をある種無邪気に称揚するやり方は凡庸だからこそ、検討されねばならない。自身の立場に忠実なその行為は果たしていかなる暴力を発動させているのか。
 |
ソリューションかベンチャーか |
一口にシェアリングエコノミーと言っても、その内実はかなり多様だ。不動産を持つ人が自身の留守の間だけ、あるいは手持無沙汰になっている余分な部屋を安価な宿泊先を探す旅行者に貸し出すエアービーアンドビー(Airbnb)を筆頭に、中古品のリユースを無料で行うもの(たとえば U-Exchange)、自動車所有者が使わない時間帯だけ貸し出すもの(たとえば Zipcar)、あるいは同じく自動車所有者が近くにいる人を乗せてあげるライドシェアと呼ばれるもの(たとえば Uber)など多岐にわたる。場合によってはここに、物理的に CD や DVD などを買うのではなく作品へのアクセス権のみを購入する音楽(映像)配信サービス(Spotify など)も含まれる。またカテゴライズの仕方も多様で、上記のように提供されるサービスの内容での区分のほかに、一般個人消費者同士をつなげる(peer to peer, P2P)か企業間でのサービスや資本、特許、労働力の「シェア」を意味する(business to business, B2B)かで分けることもあるし、「シェア」の内実がレンタルか完全無料かの違いで見ていくことも可能だ。
雑多な交換やビジネス形態を広く包含するシェアリングエコノミーだが、その一般的な説明を見る限りでは、必要としている人、提供する人、間を取り持つビジネス、という三者が存在するという点は共通している。「一般的な説明」というのは、基本的に「ビジネス書」と言われるもので、実際のところシェアリングエコノミーに関する書籍のほとんどがこのジャンルに入っている。ベンチャービジネスとしてのシェアリングの解説といった体裁をとっていない書籍を見つけるのが難しいくらいだ。こういったビジネス概説書あるいは企業指南書という体裁をベースに、資源(スペースや労働力も含む)の有効活用や大量消費文化の変革という意味での環境主義や、P2P でつながりのあるコミュニティをつくりだすという社会変革論などのエッセンスをブレンドしていけばほとんどの書籍を網羅することができる。
もちろん忘れてはいけないのが、この「新しい」エコノミーが社会全体の生産性を上げる成長戦略として位置付けられるというほとんどすべての議論に共通するコンセンサスだ。それは書籍に限らず、政府の公式見解にもはっきりと読み取ることができる。内閣官房に設置された情報通信技術(IT)総合戦略室によるシェアリングエコノミー促進室の定義を見てみよう。
シェアリングエコノミー(個人等が保有する活用可能な資産等(スキルや時間等の無形のものを含む。)を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動をいう。)は IT の普及・高度化に伴い、空き部屋、会議室、駐車スペースや衣服のシェア、家事代行、育児代行、イラスト作成のマッチングなど多様な分野で登場しつつあり、一億総活躍社会の実現や地方創生の実現など、超少子高齢化社会を迎える我が国の諸課題の解決に資する可能性があります。(https://cio.go.jp/share-eco-center/)
要するに、シェアリングエコノミーは企業から見れば新規開拓の文字どおりベンチャーであり、政府から見れば「伝道師」の言うとおり経済活性化のソリューションでもある、ということになる。実際に、ベンチャーという意味ではエアービーアンドビーやウーバーの成長は驚くほどのものだし、ソリューションという意味でも賛同者たちの未来予想がそのとおりになるのであれば何とも輝かしいものに見える。困りごとを持つ消費者は、間に入るプラットフォーム提供企業の助けを借りた提供者とつながって何かの「シェア」を受けることで用を満たすことができるし、その過程で両端の必要者と提供者は「コミュニティ」を形成し、間の企業も儲かる、一石三鳥というわけだ。ほとんどのビジネス書や政府の見解が提示する枠組みで見る限り、未来は明るいようだ。だが、本当にそうだろうか。
 |
労働者のいないビジネス |
シェアリングエコノミーについて考えていくときに注意しなければならないのは、それが広く一般的なものとなった、あるきっかけだ。シェアリングエコノミーを扱うすべての書籍で言及されるわけではないし、ましてや政府の公式見解では触れられもしないが、そのきっかけとして最も頻繁に言及されるのが、2008年の世界金融危機、いわゆるリーマンショックだ(たとえば宮崎 31)。端的に言えば、金融危機のさ中のある種の「財テク」として、あるいは職にあぶれた人びとの手っ取り早い仕事としてシェアリングエコノミーが浸透したという側面が少なからずあるのだ。たとえばボッツマンとロジャースの『シェア』では「金融危機への単なる反応ではない」としながらも、リーマンショックが繰り返し言及される。この著者らによれば、この時期にアメリカで「カーシェアの会員数は 51.5% 増加した」(19)とされており、「経済危機は、人びとがもともと必要としていたものや、それを手に入れる新しい手法を後押しした」(21)のだというのだから、金融危機がシェアリングエコノミー伸長の重要なきっかけであったことは間違いないだろう。この事実は何を意味するのだろうか。
シェアリングエコノミーを褒めたたえる議論に欠けているのは、あるいはそういった論調が見ないようにしているのは、労働者というアクターだ。いや、正確にはすでに登場しているが違う名前が与えられている。先ほど言及した「提供する人」だ。エアービーアンドビーで「ホスト」と呼ばれる「提供する人」が提供しているのは、ホテルで言えば経営管理業務、アテンド業務、清掃業務等という労働なのであり、そもそも空き部屋は労働の対価として得た賃金で購入した不動産の一部であるはずだ。あるいは、ウーバーの「パートナー」(ウーバーはドライバーをこう呼ぶ)は運転手以外のなにものでもない。もちろん広義にシェアリングエコノミーに含まれるストリーミングサービスなどの実質的なレンタル業務のほとんどはこれに該当しないが、日本政府の公式の定義にあてはまる狭義においてはほぼすべてあてはまる。これを労働者の側から見れば、「ホスト」や「パートナー」になるということは、実質的に個人事業主になることを意味する。要するにこのビジネスモデルには、「つながり」を提供するウーバーやエアービーアンドビー本社勤務の数少ない正社員以外に、労働者は存在しないのだ。この事態の意味するところは大きい。
シェアリングエコノミーを労働者という視点から理解するうえで最も分かりやすいのはウーバーの事例だろう。イギリス、スタッフォードシャーのアマゾン倉庫やサウス・ウェールズのコールセンター、そしてロンドンのウーバーに潜入取材をしたジェームズ・ブラッドワースのルポはその深刻な問題点を詳らかにしている。ブラッドワースの報告によれば、ウーバーはドライバーを「パートナー」と呼び形式上は個人事業主として位置付け、ドライバーたちにはいつどれだけの時間働くかを決める自由がある。いわば「フレックス制」勤務の究極的な形とも言える。ドライバーたちは好きな時にアプリを立ち上げ好きなだけ勤務し、ある程度稼いだら仕事を終えて家に帰れるし、長時間がんばって多く稼ぐことも可能だ。
だがこのシステムには大きな問題がある。そもそもウーバーは個人事業主として扱っているドライバーたちに登録時の研修やアプリでの管理(罰則も含む)、成績不順の際の再研修等を義務付けており、ドライバーたちを実質的に労働者として扱っている。それにもかかわらず収入は完全歩合制で、正社員に用意されるべき有給休暇や福利厚生などは一切存在しないのだ。さらに悪いことに、ブラッドワースによれば彼が潜入したロンドンのウーバーの「パートナー」たちの多くが貧しい移民であり、車を借りながらあるいは無理な借金で購入した自動車を使って労働を行っている。これではドライバーとして得る(ウーバーの仲介料を差し引かれた)収入からさらにレンタカー代金が差し引かれ、実際の収入はかなり目減りしてしまうことになる。自動車を購入してしまった場合はさらに絶望的で、借金を負った状態で不安定な収入の業態から抜け出せなくなってしまう。また、ウーバーとしては「どこでもいつでもすぐ配車」を実現するためにできるだけ多くの「パートナー」を必要とするのだから、システム上、ウーバーが提供サービスの品質向上の企業努力をすればするほど、ドライバーたちが客にありつける確率は減り、したがって収入は、下がることになる。端的に言って、ウーバーのビジネスモデルは単発仕事で成立する「ギグエコノミー」でしかなく、企業としてのウーバーの伸長は労働者であるドライバーたちの労働条件切り下げにほかならないのだ。
 |
シェアリングエコノミーに欠けているもの |
プラットフォーム(つながり)提供サービスを行う事業本社勤務以外には労働者がいない、それがウーバーの公式のビジネスモデルだ。そこに存在するのは安価なタクシーを「必要とする人」と個人事業主として最安値まで切り詰められた労働を「パートナー」として「提供する人」、そして「その間を取り持つ企業」だけなのだ。日本企業の定義にあてはまるシェアリングエコノミー企業は多かれ少なかれ似通ったシステムとなっている。これでは、控えめに言っても労働力の安い買い叩きでしかないのではないだろうか。だがそれだけではない。ここで問いたいのは、果たしてこれが「シェア」と言えるのか、という点だ。
そもそも、人間が社会で生活するうえでは人は必ず誰かに依存している。どれだけ農業に長けていても家を作れなければ雨風はしのげないし、快適な暮らしなど望むべくもない。私の依存は誰かの労働によって支えられる。わたしたちはこの依存関係をお互いにシェアすることで社会生活を送っている。依存と労働は個人の社会性の最低条件なのだ。こういった物言いは原始的な共同体モデルと感じられるかもしれないが、この原則は見えづらくはなっているものの、現在も変わらないはずだ。この労働と依存を媒介するのが労働の生み出す価値でありそれに見合う賃金だ。少々突飛なイメージかもしれないが、こうしてみるとシェアリングエコノミーに欠けているものが見えてくる。もうはっきりと言ってしまっていいだろう。シェアリングエコノミーに欠けているのは、どれほど逆説的に見えようとも、「シェア」、正確には、この労働と依存の関係を表裏のものとして共有するという意味での「シェア」だ。シェアリングエコノミーでは、わたしたちは「サービス提供者」として「サービスを必要とする人」と「つながる」ことはできるが、それぞれの労働と依存をシェアすることはできない。正確には労働/依存の関係を「シェア」しているという点が、つまりは社会性が見えなくなってしまうのだ。
ではどうすればいいのだろう。「シェア」がなければわたしたちの関係はギグエコノミーならぬギグシェアリングに終わってしまう。社会にコミュニティは立ち上がらないように思われる。思いつく限りでは処方箋はない。だが、これからも拡大と深化を続けるであろうシェアリングエコノミーにおいて、希求されながらも決定的に欠ける「シェア」や「コミュニティ」そして社会の全体性を諦めず手放さないこと。それがまずはわたしたちで共有できる出発点なのではないだろうか。目に見える製品を媒介にした目に見えない関係ではなく、シェアリングエコノミーはサービスという目に見えないものを通して目に見える関係にわたしたちをますます投げ出していくだろう。目の前に人がいるということ。まずはこれを確認し「シェア」していくことが足場になるのだろう。
〈参考文献〉
|
西 亮太(にし りょうた) 中央大学法学部准教授。専門はポストコロニアル批評。論文に「森崎和江のことば――運動論とエロスのゆくえ 1」、『詩と思想』第3巻374号(土曜美術社、2018年)118-124頁など。翻訳にヘザー・ブラウン「マルクスのジェンダーと家族論」『ニュクス』第3号(堀之内出版、2016年)54-65頁など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |