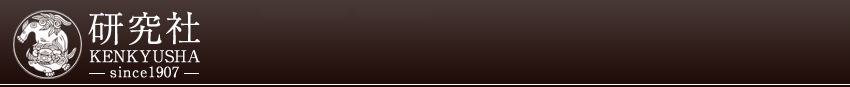

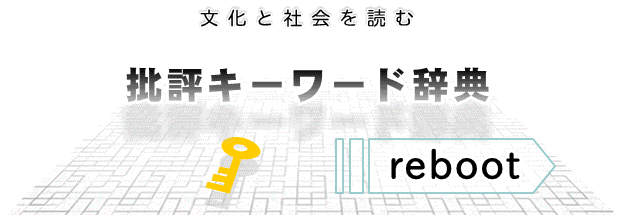
第7回
 | 映(ば)える 〈前編〉 |
「〜 が映(ば)える」といった言い方が、ここ一、二年ほどの間に、とりわけ若い人びとの間で盛んになされるようになった。この言葉は、『三省堂 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語 2018」』の新語大賞に選ばれ、その前年の2017年には「インスタ映え」が、ユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞に――「忖度」と並んで――選ばれている。「映(ば)える」は、この「インスタ映え」や「SNS 映え」の後ろの部分が動詞化したものである。
「映(ば)える」のもととなった「インスタ映え」とは、SNS のひとつであるインスタグラム上で、他ユーザーから好反応をもらえるようなイメージのあり方を指す。インスタグラムは2010年10月にサービスを開始し、当初は iPhone でしか使用できなかったが、2012年4月から Android にも対応し(また、同時期にフェイスブックに買収された)、2014年2月には日本語版が開設された。[1] このアプリケーションで新しかったのは、スマートフォンで撮影した写真をそのままアプリ上で加工して投稿まで可能だったこと、つまり撮影・加工・投稿が一本化されたことである。それまでにも、フリッカーなどが写真を管理し他ユーザーとつながるアプリとして存在していたが、そのようなアプリでは、写真撮影機能のみのデジタルカメラで撮影された写真データをいったんパソコンに取り込み、投稿するという形が一般的だった。インスタグラムは発表当初、スマートフォンで撮影された写真をヴィンテージ写真風に加工できるフィルターによって人気を博したのち、2011年には自撮りが各国で流行し、2013年には自撮りを意味する英語 “selfie” が『オックスフォード英語辞典』の「今年の言葉」に選ばれるほどに広まった。日本でもインスタグラムに関わる言葉が流行語大賞に選ばれたことからもわかるように、そのアプリの利用者数は2017年までには増加しており、現在では自撮りだけでなく、インスタ映え/SNS 映えするカフェ・飲食店、メイク、インテリア、イベント、展覧会、コンサート、観光スポットを求める消費行動が目立ち始め、そのような消費を拡大するために、各企業のマーケティング部門が積極的に「映(ば)える」演出をするようになっている。
三省堂の「今年の新語 2018」の選評が掲載されたウェブサイトでは、『新明解国語辞典』編集部、『三省堂国語辞典』の飯岡浩明、『三省堂現代新国語辞典』の小野正弘、『大辞林』編集部がおのおの、「ばえる(映える)」の定義を与えている。これら四つの定義は、二種類に大別できるように思うが、一方は、ある写真や映像がひときわ引き立って、良く/きれいに/おしゃれに見える、という定義である。こちらは、動詞と形容詞の違い、単一の SNS に限定していないという違いこそあるものの、「インスタ映え」の意味とそれほど変わりはないように思われる。より質的に新しいと思われるのは、もう一方である。それは、風景や人物、料理などのある現実の対象が、SNS に投稿したくなるほど驚きを与えたり印象的であったりする様子である、という定義である。この定義からは、ある被写体を撮影しウェブ上でシェアする論理を前提とした現実の知覚の仕方が、それを動詞一語で即座に表現しなければならないほど、広まっているということがわかる。つまり、ここでは「光を映して美しく輝く」(広辞苑参照)という濁点なしの「映える」の意味が、SNS の論理に媒介されている。「写真映え」という言葉は以前から存在し、それも写真撮影を前提として現実の風景などを眺める視覚を意味していた。それゆえ、「映(ば)える」という感性そのものは、これまで変化を遂げてきた知覚からの完全な断絶ではない。ただ、現在ではカメラは携帯電話に内蔵されてだれもが持ち歩き、またソーシャル・メディアを通して即座に投稿可能であるため、新しい状況が生まれてもいるだろう。そして、これは重要なことだが、これらの新語は技術的変化のみを契機としているのではなく、より深い社会と文化の変化から生じているように思われる。それはどのような変化で、そこから生じたこの言葉は、わたしたちのどのような経験を刻み込み、どのような願望を表しているのだろうか?
 |
コミュニケーションとしての写真――ソーシャル・フォト |
先進資本主義国では特にスマートフォンの普及が爆発的に進み、現在では、イメージの撮影や交換が日常的な行為となっている。そのようにしてネットワークに接続された携帯電話によってやりとりされる写真は、日常的なコミュニケーションの一部として用いられるようになってきている。どういうことだろうか。この変化は、デジタル化以前に写真が担っていた中心的機能と比較するとわかりやすい。デジタル化以前には、写真は形ある客体(もの)として、(しばしば特別な)出来事を記録するために撮影され、保管されるのが主たるあり方だった。写真がまだアナログで、データとして即時的にだれかに転送可能ではなかった時代には、プロ写真家によって撮影されたイメージが公的領域に出るまでには一定程度の時間がかかったし、その公的領域もある程度予測可能で限定的なものだった。ジャーナリズムにおいて撮影された写真ではなく個人的な写真、たとえば個人写真の代表例である家族写真などは――セレブリティたちの一部を除けば――近親者や友人、知人以外には公開されることは滅多になかっただろう。しかし、インターネットに接続できるカメラ付き携帯電話が普及し、それにより撮影された写真を共有するソーシャル・メディアが一般化し始めると、そのような状況は変化する。
現在、特に若者のスマートフォンの使用において写真は、現実を記録するという目的それ自体というよりも、撮影されるときどきの経験を共有するための手段となっている。ここでは、現在支配的になってきているこのような流動的で表現的な写真のあり方を、メディア研究者ネイサン・ジャーゲンソンにならって、「ソーシャル・フォト」と呼びたい(これは、「ソーシャル・メディア」などの「ソーシャル」とかけた呼称である)。繰り返すが、ソーシャル・フォトとは、なんらかの特別な出来事の記録を残すことよりも、日常生活における一時的なコミュニケーションを目的とした、記録よりも表現に近い写真の使用であり、話し言葉に似ている。これまで、写真はある瞬間を思い出すための「メメント」の役割を主に担っていた。それがいまでは、情報というよりも撮影者の一視点からの表現として、その人物の経験を伝達する役割が前景化してきている(Ritchin 11)。たとえば、食べ物の写真であれば、撮影者がだれであり、何を経験しているのかを伝えるコミュニケーションの一部となっている、というように(Jurgenson 16)。そして、ソーシャル・メディア上ではつねに大量のイメージが流れているため、そのような写真もつねにその流れの一部となり、過ぎ去ってゆく。この点も、これまでアルバムや空き箱に入れられていた、ものとしての写真の静的容態とは異なっている。スマートフォンで撮影された写真のほとんどは長期間保存されるものとしてよりも、その場でシェアされるかディスプレイ上で見られるために存在するようになり、大量のデータ保存容量は、そこに入れられる写真を記憶させるよりはむしろ忘れさせるよう機能している。それゆえに、こうしたソーシャル・フォトにおいては、すべての写真はそれぞれ同じようには保存されない。そうではなく、選別と削除が当たり前の行為となり、そのなかで残される写真はとりわけ重要なものとして扱われる(Jurgenson 51-52)。当然、ある出来事を思い出すための写真という以前から存在した役割が消えることはないが、現在の日常的な写真の用いられ方は、このようなコミュニケーションの方へとシフトしてきている。
このようなソーシャル・フォトの扱われ方は、見た後に捨てられる絵はがきに似ている(Van Dijck 62)。ただ、絵はがきと異なるのは、そこには多くの場合、風光明媚な場所や有名な観光地の写真やイラスト、絵画が印刷されるのとは対照的に、カメラ付き携帯電話で撮影される被写体はそのような特別な対象に限定されず、日常生活のなかのささいな被写体であることが多いという点だろう。このような被写体の変化は、多くの人がカメラ付き携帯電話を所有するようになり、「「誰かに見せよう」と他者を志向して写真を撮る、というこれまでフォト・ジャーナリストや特別な愛好家だけが持ち得た心性を、普通のひとびとがもつ」ようになったことが一因となっている(有本・岡部 78)。2000年に J-PHONE がカメラ付き携帯電話を発売して以来、カメラ付き携帯電話の利用者はしばしば、日常のなかにおけるちょっとした瞬間や予想外な驚きの瞬間、美しく感じたもの、一風変わったもの、古びた家屋や風景などを気軽に撮影するようになった(Okabe and Ito; Murray 155)。そのような写真は、家族や友人、親しい者に送信されるか、ソーシャル・メディアで共有される。このようなイメージの交換を通したコミュニケーションは、そこでつながっている人びとの間での関係性を維持し、ときには強め、あるいはそれまでなかった関係性をつくり出しもするだろう。[2]
そして、ソーシャル・フォトの実践には、他者とのコミュニケーションのなかで生じる、みずからのアイデンティティの生産・維持・管理も含まれる。このようなアイデンティティの維持管理は、しばしば SNS における自己イメージの提示を説明する際によく用いられる社会学者のアーヴィング・ゴフマンの用語で言えば、「印象のマネジメント」である。特定のオーディエンス(フォロワー)の視線をしばしばユーザーが内面化しているソーシャル・メディアにおいては、とりわけその側面は強くなるだろう。ただ、病気の時のセルフィーを投稿するなど、必ずしもユーザー自身のイメージを良いものにするためだけにソーシャル・フォトは行われるわけではなく、良い・羨望される自己イメージの提示にだけは還元されない場合も多い。
このようなソーシャル・フォトという文化的実践のなかで、「映(ば)える」イメージの生産とは、もっともわかりやすく他者を志向した写真の生産であると言える。「映(ば)える」写真は、それがときに他ユーザーからの承認を求める自己顕示的なものであったとしても、他者とある種の経験の瞬間を共有したいという願望を有している。つまり、それは他者とのつながりの希求や、ある種の共同体への願望を示していると言えるだろう。ただ、その共同体は、最終的には、社会において真に共通のものであるとは言えない。どういうことだろうか。まずは、流行語大賞にまでなった「インスタ映え」するイメージが具体的にどのようなものなのかを検討し、その「美学」がいかなる文化的力学のもとにあるのかを考えたい。
 |
「インスタ映え」の美学 |
インスタ映えの定義そのものはあいまいであり、その言葉が用いられる文脈によって異なる場合が多い。その語が狭い意味で使われている事例を見れば、仕事を中心とする日常生活のなかでは訪れることの難しい観光地や、ふだん食べないような料理、つまり特別な瞬間を写したものが多いとされる。反対に、広い定義では、他ユーザーの写真の流れのなかに埋もれない目立つ写真がインスタ映えであるとされ、その語が指示するものは文脈によってかなり振れ幅がある。それでも、インスタ映えするとされるイメージには一定の方向性はあると思われるため、この節では、「インスタ映え」とグーグル検索をするとトップに出てくる「SNS 映え観光情報サービス」の「スナップレイス」というウェブサイトの(長大な)解説から、どのようなものがインスタ映えするとされているのかを見ていきたい。このサイト自体は日本旅行や H.I.S. と提携しているため中立的なものとは言えないが、SNS を利用するユーザーのデータを分析した上でどのような画像が「インスタ映え」とされるかを解説している点で、おおまかな特徴をつかむことを可能にしてくれると思われる。
スナップレイスにおける解説はかなり細かい項目に分けられているが、写真のタイプとしては大別すると、「フォトジェニック」系と「ネタ・面白い」系の二種類に分けることができ、さらにそれぞれを、1)被写体、2)撮影方法、3)加工方法という三点から以下のように整理できるように思われる。
これらの特徴からわかるのは、「インスタ映え」する写真とは、フォトジェニック系であろうとネタ系であろうと主題や被写体がわかりやすく、色調によるインパクトを与え、一見して多くの人が好感や驚きをもって対面する非日常性を感じさせるイメージであるということだ。[3] このような美学的特徴は、社会学者ピエール・ブルデューが『ディスタンクシオン』において提示した「大衆「美学」」に近いように思われる。彼のこの言葉において美学という語にかっこがつけられているのは、より真正であるとされ権威を持つブルジョワ階級の美学にとって重要なのが形式的要素であり、それとは対照的に、大衆「美学」においては内容が重視され、一般的に「美学」と考えられるものからは外れるからである。ブルジョワ階級の美学は、感覚的快楽と距離を取ることを基礎とする。それとは反対に、大衆「美学」においては、感覚的な楽しみ、魅力や感動が美的判断と直接結びついている――現代でも影響力を持つ美学の議論を展開したイマヌエル・カントにとっては、色彩は形式に対して二次的なものにすぎなかった(ブルデュー 53-68)。
ブルデューの議論は、ブルジョワ美学と大衆「美学」のどちらが優れているかという話ではなく、このような「意識や言説の手前で」生じる趣味判断の違いが社会的な階級関係の再生産から生じていることを示すものだ。この意味での「趣味」とは英語では “taste” であり、現在では「消費者」と切り離すことのできない考えである(その語義は日本語の「テイスト」という言葉にもわずかに感じられるだろう)(ウィリアムズ 544)。何を美しいと判断するか、何が「映(ば)える」かを判断することは、趣味判断のひとつであり、美学的な問題である。そして、そのような趣味の問題とは、ブルデューが分析したように、階級的な問題である。
前節で言及したように、あるユーザーがインスタ映えを目指して投稿するという行為には、その瞬間の経験をフォロワーや潜在的なユーザーたちに伝えたいという願望が含まれている。それは、一定の趣味判断を共有する美学的な共同体の一員でありたいという願望でもあるだろう。しかし、インスタ映え的な美学は、階級社会が存続しているがゆえに、社会のなかで真に共通のものであると言うことはできない。次の節では、大衆「美学」としてのインスタ映えとは異なる別の趣味判断のあり方として、雑誌 Kinfolk に影響されたインスタグラム・ユーザーの写真の美学を検討する。
〈注〉
〈参照文献〉
|
田尻 歩(たじり あゆむ) 明治大学商学部ほか非常勤講師。一橋大学大学院言語社会研究科博士後期課程修了。専門は写真理論および20世紀後半以後の芸術理論。論文に「理論と実践の間の写真――アラン・セクーラの写真理論再読」『年報カルチュラル・スタディーズ』第6号(カルチュラル・スタディーズ学会、2018年)103-124頁など。翻訳にピーター・ホルワード「自己決定と政治的意志」『多様体 1』(月曜社、2018年)69-84頁など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |