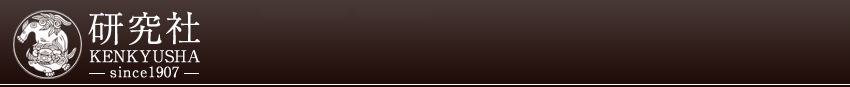

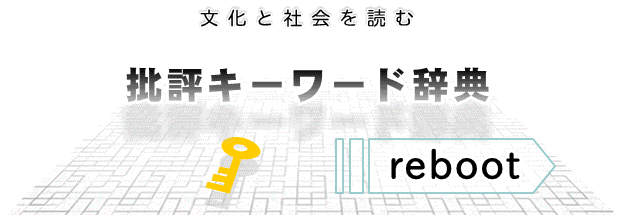
第8回
 | 映(ば)える 〈後編〉 |
 |
自己啓発本としてのスロー・ライフスタイル雑誌 Kinfolk |
Kinfolk は、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにおいて2011年7月に、当時20代前半だったネイサン・ウィリアムズを編集長とし、彼の元パートナーのケイティ・サール、その友人ダグとペイジのビショッフ夫妻らによって創刊された、インディペンデント雑誌である。[1] はじめは「小さな集い」を、Volume 8 からは「小さくて新しい発見の日々」をキャッチコピーにしたこの雑誌は、「生活をシンプルに、コミュニティを豊かにし、友人や家族とより多くの時間を過ごす方法を探求する〔……〕スロー・ライフスタイル雑誌」である(Volume 14 の表紙折り返し部分、Bean et al. (83) に引用)。2012年末の発行部数は2千部だったが、徐々に世界中で読者を獲得し、2013年には7万部、2016年には8万部発行されている。[2] 日本においては2013年6月出版の Volume 8(日本特集)から日本版『Kinfolk Japan Edition』の出版が始まるが、英語のオリジナルも創刊号の頃から売れていたという。
20代半ばから30代半ばのクリエイティヴ産業従事者をターゲット読者とするこの雑誌は、真正性(ほんものらしさ)や手仕事、対面的コミュニケーションを重視する価値観にもとづいて、「質の高い」時間――それが「スロー」の意味するところだ――の過ごし方を提示しようとする。記事の内容としては、各号で特集が組まれ、職人、建築家、アーティスト、起業家などのクリエイティヴ産業で活躍する人びとへのインタビューと彼ら彼女らのスローなライフスタイル、シンプルだがオーガニックな料理レシピ、Do-It-Yourself のすすめ、日常的なもの(光、影、時間など)に対する意識を変えるヒントとなるコラムなどである。それらの記事は、創刊者のひとりダグ・ビショッフが言うように「ある種の自己啓発(self-help)の内容」である。ただ、ライターのカイル・チャイカが Kinfolk で革新的なのは記事ではなくヴィジュアル的側面であると述べているように、その雑誌にとっては視覚的要素が非常に重要である。編集長ネイサン・ウィリアムズは「わたしたちのアプローチは親密で私的」であると述べるが(『Kinfolk Japan Edition』)、彼は、読者がその雑誌を読む体験それ自体が、友人たちと夜を過ごす時に抱く感情と同じものを喚起するものにしようとしていたという。具体的には、(現在の誌面とはかなり異なるが)初期のレイアウトにおいては文字が非常に小さく、余白がたっぷりと取られており、これにより読者がゆったりとした時間を過ごすことが意図されていた。
そのようなレイアウトに加えて、雑誌がもたらす雰囲気そのものを規定しているのは写真である。被写体はさまざまだが、特徴的なものを挙げると、カフェラテが注がれた陶器のマグカップ、花でいっぱいになったバスケット、鍵のかかっていない自転車、アイスの代わりに花が入れられたアイスクリームのコーン、などである。消費文化研究者のジョナサン・ビーンらが指摘しているように、この雑誌の写真においては、製品の包みや値札、ブランドのロゴ、コンピューター、携帯電話、電子レンジなど、つまり、大量消費物やテクノロジーといったスロー・ライフに反すると考えられるようなものはほとんど映されない(Bean et al. 83)。創刊号あたりでは、ざらついて温かみのある色調のヴィンテージ風の写真が多く、ノスタルジックな雰囲気が強かったが、Volume 14 が発売される頃には、アートギャラリーのようなミニマリスト的空間で撮影される写真が登場するようになる。そのギャラリースペース的な場所での撮影は、しばしば単色の壁を背景にして、事物や人が単体で映し出される。そうして映されるモデルの顔はしばしば目から上の部分がフレームから外されるか表情が見えないようにされており、ミステリアスな雰囲気を醸すように撮影される。これらの写真のあり方が読者を刺激し、インスタグラムで雰囲気の似た写真が多数投稿されるようになったが、それを検討する前に、まずこの雑誌における「スロー・ライフスタイル」がどういうイデオロギーなのかを考えておきたい。
この雑誌が創刊されたのは、2010年10月にインスタグラムが発表されてから9ヶ月後にあたり、先進資本主義国家においてインターネットが日常生活のなかで存在感をいっそう増し、デジタル化がさらに進んでいく途上の時期であった。そのような状況の中で、ウィリアムズらは、紙の雑誌という触覚的な経験を前景化しながら、家族や友人たちと一緒に――ただ、一人であることが否定的に捉えられることは決してない――食事をとるといった対面的なコミュニケーションを促進し、同じような価値観を持つもの同士がつながることが重要だと考えた。彼は、スマートフォンを含むコンピューターとの対面時間が多くなったことを問題視し、それへのオルタナティヴとして触覚性や直接的交流を重視しているが、このような価値観は、デジタル化が社会に浸透したからこそ生じてきた反応であると言える。別の言い方をすれば、現代社会における技術やそれにまつわる社会関係をめぐる問題を、資本家階級に有利なように技術が利用される資本主義経済や企業による技術の独占といった問題として扱うのではなく、個人的なライフスタイルとして解決しようとしているということだ。
このように、雑誌が広めようとしているのは、特定の商品ではなく特定のライフスタイルとそれを支える価値観であり、そしてその経験である。このような、ものとしての商品の消費ではない、ライフスタイルの消費は今では支配的な消費のあり方になっている。社会学者の米澤泉は、高価なハイ・ブランドの服を買ってルックスを他の人びとと競い合う1980年代日本のファッション消費のあり方から、1990年代後半から徐々に広がり始めた、「オーガニック」であったり「インテリジェント」であったりするライフスタイルそれ自体を購入するライフスタイル消費への移行を分析している。その流れに敏感だったファッション誌は服よりもライフスタイルを扱い始め、1998年に始まる『カーサブルータス』、2003年に出版された『ku:nel』など、ライフスタイル誌の市場がどんどん拡大した。(そういった雑誌の読者にとっての)消費の場の焦点が「くらし」へと移動するなかで、日本においては東日本大震災を契機として、多くのライフスタイル雑誌はより内向きになり、日本文化や自然、パンなどの食をテーマとしていく(阿部 「暮らし」220、米澤 第四章)。このようなライフスタイル消費における主要なテーゼを要約すると、「単に日常生活を慌ただしく送る」のではなく、「じっくりと時間をかけて日々の生活を味わうこと」――つまり「ていねいなくらし」をすること――であると表現できる(米澤 217)。ここでは、漫然と過ごしている日常に意識的になり、そこに手を入れることで別の生活を手に入れるというプロセスが主題となっており、Kinfolk もそれを共有しているだろう。
みずからの生活に自覚的になり、手を加えることで別の生活を手に入れるというこのような考えは、自己啓発本的な発想と重なる。実際、Kinfolk の記事内容は自己啓発本に近く、「自己啓発本を捨てて、時を超えた日本古来のコンセプトを再確認」という一節が登場するように、読者層も近いだろう(『Kinfolk Japan Edition』22)。社会学者の牧野智和は、自己啓発本が何を主題としているのかを以下のように要約する。「日常の、普段の、今ここの生活を疎かにしているのではないか、そこに自覚的になることで、心理的な効用やビジネスに関する能力等が獲得できるのではないか、いやできるのだ」(牧野 4)。それを実践する人びとは、そのように自己や生活を見直すことで、漫然と生きるとされる大多数の人びととみずからを差異化する。Kinfolk で提唱される生活の実践は上層労働者のマインドセットを養う側面が強く、惰性で過ごす日常生活を脱却して他者との差異化を促すという意味で、自己啓発的想像力とつながっていると言える。
牧野は、自己啓発本がホワイトカラーを対象読者としてつくられるミドルクラス文化の一部であると考えるが(30)、読者のおよそ7割がクリエイティヴ産業従事者の Kinfolk もそうであると考えてもよいように思われる。ただ、ここでいう「ミドルクラス」とは、ある人の所得や財産から客観的に導き出される特定の階層を静態的に表すものではない。階級とは、社会学者の渋谷望が述べるように、資本の圧力に対して人びとが採用する戦略であると同時に、そのなかでみずからをつくり上げていくプロセスである。そのようなものとして捉えられた階級としてのミドルクラスとは、彼ら彼女らを日々疎外し損なう「資本の圧力」から「「個人として」(=個人の能力によって)抜け出すために日々努力をしている人々のこと」を指す(渋谷 18、太字ママ)。かつての日本社会の神話である「総中流社会」において中流であるという意識をミドルクラスの意識とみなす渋谷は、そのような意識が、ある種の否定の身振りを通して獲得されると、ピエール・ブルデューの分析を援用して指摘する。
『ディスタンクシオン』においてブルデューは、ブルジョワ階級、プチブル階級、庶民階級と三つの階級に分けてそれぞれの階級の趣味判断のあり方を分析したが、そこでプチブル階級は、庶民階級的なあり方を否定し、みずからを差異化することによってブルジョワ階級に近づこうとし、そのためつねに不安にとりつかれたものとして描かれている。渋谷によれば、ミドルクラスの心性とプチブルの心性は類似しており、そのような自己に対する不安、上昇志向がミドルクラス文化を特徴付けるものである。デジタル・ガジェットとインターネットに埋没せず、近親者との時間を大切にし、手仕事や直接的コミュニケーションを基盤とした「本当の生」を生きるようすすめる Kinfolk も、そのようなミドルクラス文化に含まれるだろう。
 |
Kinfolk 的な美学は「映(ば)える」のか? |
インスタグラム上では、Kinfolk に影響された写真が刊行後から徐々に、しばしば「#kinfolk」というハッシュタグ、さらに「#liveauthentic」(本当の生活を生きる)というハッシュタグとともに投稿されるようになった。そういった写真の多くは、被写体としては陶器のカップに注がれたカフェラテやコーン付きのアイスクリーム、色味を抑えた洗いざらした色調、単色の壁の背景を選び、テーブルやベッドの上に物がアーティスティックにちらばった状態を真上から映す、あるいは身体の一部を写し込むなどの特徴を持っている(例としては、その雑誌から影響を受けたインスタグラムのユーザーの投稿を集めたサイト、The Kinspiracy を参照)。[3] このような、Kinfolk 風の写真をインスタグラム上で再現することは、加工機能も併用すると比較的容易なため、その創刊者たちも驚くほど急速に投稿が増えていった。そのようなイメージの多くは、撮影場所としてはカフェや自室などの日常的な場面が多く、屋外の場合でも、有名な場所やあからさまに消費行動を思わせる場所は選ばれない。ここでは、前回見たカラフルだったり驚きをもたらしたりする「インスタ映え」的な写真の多くとは異なり、何が主題となっていて、どこに価値を見出せば良いのかは、(その美学に共感する者以外には)明白ではない。つまり、そのような写真の多くは、インスタ映えする写真とは異なる美学を示している。結論から言うと、Kinfolk 的な美学は、上で述べた他者とは差異化された経験、日常生活に手を加えて得ることのできた「上質な」経験を伝達するための文法として広まったように思われる。
アーカイヴしたウェブサイト The Kinspiracy より

© Summer Allen
2016年の時点でチャイカは、「#kinfolk」というハッシュタグで結ばれるコミュニティがあまりに拡大してしまい、そこでの投稿が、雑誌が提示する生き方の実践というよりも、たんなる視覚的スタイルを模倣した表層的なものになっていると嘆いている。しかし、このような趣味判断以外に確固たる基盤を持たない表層的でいい加減なつながりこそ、美学的コミュニティの特質をよく表しているように思われる(バウマン 100-110)。インスタグラム上のそのコミュニティに特徴的な投稿として、Kinfolk の雑誌そのものを部屋の一角に配置するか、他のものと雑多に同居するよう――それと同時に美しいデザインに見えるように――テーブル上に配置し、その様子を Kinfolk 風に撮影したイメージがある。このような写真は、同じような価値観を共有するコミュニティに投稿者が参加していることを示すコミュニケーションであると同時に、そういった価値観を持っているという自己提示であると言える。ある意味で、その写真集のようなつくりの雑誌は内容以前にインテリアの一部なのであり、それを買った人は、雑誌が表象するスロー・ライフスタイルに一瞬で参加できるようになる(という感覚を得る)。生活の細部を切り取る写真などは、2003年創刊のライフスタイル雑誌『ku:nel』あたりから存在したが(阿部「『ku:nel』」)、Kinfolk 的な美学と SNS の相性が良かったのは、日常の細かな経験を切り取るというソーシャル・フォトの論理を基盤とするインスタグラムの流行と時期的に重なり、そして、その雑誌の写真が、差異化された経験に対して、一般読者が模倣可能な視覚的文法を与えたからだろう。
こういった Kinfolk 的なイメージに対して、「インスタ映え」という形容がなされることはそれほど多くないように思われる。その雑誌の美学を好む人びとは、流行語大賞に選ばれるような語彙を、漠然と想定される「大衆」とみずからを差異化するために使おうとしないかもしれない。とはいっても、これはどちらも、ソーシャル・フォトの異なる現れ方でしかない。現象としては、ある瞬間をフレーミングしシェアする、一定のコミュニティ内でのコミュニケーションという点では同じものである。
 |
ソーシャル・フォトの社会・文化的条件と「映える」の未来? |
改めて整理すると、「インスタ映え」写真の多くは、ネタ的な面白い写真からカラフルなカフェやレストラン、非日常を感じさせる場所を映して他ユーザーから賞賛を集める「大衆「美学」」にもとづいたイメージだった。他方で、そのようなわかりやすい主題や高い彩度などの視覚的特徴を排し、「ていねい」に生きられた日常のなかで見出された美的な瞬間や、(デジタル化された世界から一時的に避難して)ゆったりとした時間を過ごす、「大衆」的経験とは差異化された経験を伝えるイメージを提示するのが Kinfolk 的なミドルクラス文化の美学であった。[4] しかし、このふたつの美学の境界はそれほど固定されたものではない。たとえばアイスクリームという主題や、壁を背景にする、足元を映す、テーブルの上のものを真上から撮るなどの Kinfolk 的美学は、すでにインスタ映え写真にも採用されている。合衆国やヨーロッパの一部においては、Kinfolk 的な美学はすでにカフェやスーパーの広告に取り入れられ主流になっており――その大衆化ゆえに、2016年に雑誌の劇的なデザインの変更があった――ふたつの美学の間の境界は流動的なものであって、ここで記述したものは現時点の整理にすぎない。ただ、そのふたつはどちらも「映える」という語が含意する経験の一端を明らかにする現象であり、同一の社会的・文化的条件から生じている。
その条件とは何だろうか? それは、たんにスマートフォンの普及や SNS の登場といった技術的変化以上のものである。現代のデジタル化した写真とコミュニケーションの結びつきの要因は、メディア研究者のヨゼ・ヴァン・ダイクによれば、1960年代後半から1970年代初頭に始まるさらなる消費社会化によって促進された、経験の個人化とその経験の質の強化にある(Van Dijck 62)。このプロセスは徐々に進行していった。1960年代後半あたりからテレビが一般家庭にも広がり、都市が広告などの記号で埋め尽くされていくようになり、日常生活にさらにイメージが溢れるようになってきた。そのように商品とイメージが日常のあらゆる場面に入り込んでくるようになると、1980年代以後その傾向がより顕著になるが、みずからのアイデンティティそのものも消費の選択によって変更可能であると捉えられるようになり、伝統的共同体からの分離がいっそう進むことで個人主義が促進される。[5] そのなかで、消費の経験はより個人化し、その経験の強度は増していくだろう。
ヴァン・ダイクは、経験の個人化に言及する際、B・J・パインII と J・H・ギルモアによるマーケティング論『経験経済』に言及している。パインらの主張は、消費者が五感を総動員して記憶しようと努める経験を売るべきだ、なぜなら経験は個人個人で異なっているから、というものだ(そのもっともわかりやすい例はディズニーランドだろう)。戦後、洗濯機や掃除機などの製品が初めて登場した時代には、それらを買わせるための広告においては、消費者が商品を得たあとで変化した生活を想像させる宣伝がなされただろうが、そういった製品がすでに日常のものになった社会においては、商品を通して得られる個人の経験がセールスポイントになる。上で見たライフスタイル消費もそのような流れのひとつであり、ある商品が果たす機能そのものよりも、それに付与された物語やライフスタイルが考慮に入れられる消費のあり方である。
ジャーゲンソンは、ソーシャル・フォトの勃興が、「わたしたちの見方、話し方、考え方へのいっそう深い、そして親密な形でのイメージの浸透」であるとしている(Jurgenson 11)。彼は、そのようなイメージの侵入によって、ソーシャル・フォトの論理は、新しいやり方でわたしたちの精神を組織し、わたしたちはソーシャル・メディアにポストすることを前提として世界を眺めるようになると述べる。その視覚のもとでは、あらゆる生の瞬間が記録されうるものとして、そして、記録のために経験されるようになる。それは、あらゆるものを潜在的なイメージとして見ることだが、ソーシャル・フォトの効果は、人が世界を経験する仕方を、人がある瞬間を重要・楽しい・意義深い・価値あるものとして認識する仕方を条件づける。と同時に、そのような認識は、人びとを「自分自身の経験の観光客」になるよう促す点で、あらゆる瞬間を消費することでもある(37)。
ただし、彼が記述する、あらゆるものを携帯カメラで記録可能であると考える視覚性の浸透も、その質を問わなければそれほど新しい事態ではない。19世紀半ばからの写真産業と観光産業の相互的な発展のなかで、世界は絵のように把握されるようになり、あらゆるものを対象化する「観光のまなざし」が支配的になった(アーリ、ラースン 258)。その流れのなかで近年質的により新しいのは、ジャーゲンソンが言うように、そのようなまなざしが撮影者の日常生活の細部までをも対象とし、日常のあらゆる瞬間をフレーミング(消費)可能なものとして捉え、そのイメージがその人の感情の流れを表すとみなされるようになったことだろう。もちろん世界においても一国内においてもスマートフォンの浸透は不均等であるため、このような記述に誇張的なところがあるのはたしかだ。ただ少なくとも、「映(ば)える」という言葉の流行は、日本社会においてそのような視覚が支配的になりつつあることを表現している。
その言葉が、他者とある瞬間を共有したいという願望を示している点で、ある種の集団性の希求を表しているのはたしかである。ただ、見てきたように、そこで望まれる集団がそのまま趣味判断を基盤としたコミュニティである場合には、階級的に分断されている。ソーシャル・メディアは――抵抗運動に用いられることが可能である一方で――現実社会の経済格差やあらゆる種類の差別を反映し再生産するため、そのような願望が解放的な意味で実現されるためには、根底にある社会関係と社会構造そのものの集団的変革が不可欠である。それゆえ、以下のように問い続ける必要があるかもしれない。無階級社会における「映(ば)える」とはどのようなものか?
〈注〉
[1] この節の Kinfolk についての情報は、主に萩原、Bean et al.、Chayka、Howarth に依拠している。
[2] このような変化のため、雑誌自体のデザインや内容も変遷している(細かな変化は Bean et al. を参照)。本論では、劇的にデザインが変化する2016年(Volume 22)までの Kinfolk の美学を念頭に論を進める。
[3] ウェブサイト Kinspiracy のタイトル下にある説明 “KINFOLK MAGAZINE: MAKING WHITE PEOPLE FEEL ARTISTIC SINCE 2011(2011年から白人を芸術的に感じさせてきた雑誌 Kinfolk)” からは、人種的な排他性がうかがえる。これは雑誌そのものの白人性にも関わっている。現在では登場するモデルは多様になってはいるものの、初期、とりわけVolume 7までは白人のモデルばかりで、そのことが批判されていた(詳しくは Chayka を参照)。
[4] 時間軸的には、「インスタ映え」的なイメージの生産は Kinfolk 的美学よりもあとに生じたが、どちらもこれまでの社会と文化の変化を反映し、デジタル化と SNS の登場に対応した現象であり、関連しあうものとして分析可能であると考える。
[5] 1960年代後半からイメージが日常に浸透し始めた過程に関しては上野を参照。また、1960年代後半から1970年代前半にかけて、テレビを介しての一家団らんが、しばしば地方出身者で構成される核家族の結合性を高めたという事実が指摘されているが(井田)、それも隣人や親戚などを含む伝統的な共同体からの分離の一過程を示しているという意味では、経験の個人化につらなる系譜であると考えられる。
〈参照文献〉
|
田尻 歩(たじり あゆむ) 明治大学商学部ほか非常勤講師。一橋大学大学院言語社会研究科博士後期課程修了。専門は写真理論および20世紀後半以後の芸術理論。論文に「理論と実践の間の写真――アラン・セクーラの写真理論再読」『年報カルチュラル・スタディーズ』第6号(カルチュラル・スタディーズ学会、2018年)103-124頁など。翻訳にピーター・ホルワード「自己決定と政治的意志」『多様体 1』(月曜社、2018年)69-84頁など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |