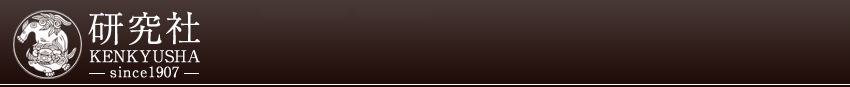

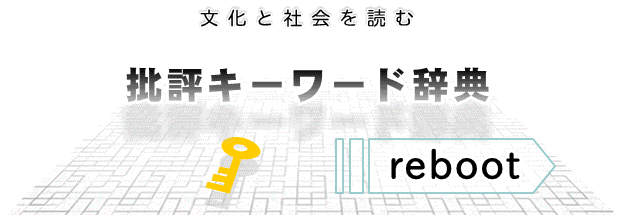
第10回
 | ボランティア |
日本語におけるボランティアとは、災害支援のような社会的行事に、自発的に参加する人を意味する。とくにその活動に無料で参加する有志を指す。これは、ボランティアが、自由意志を意味するラテン語の voluntarius を語源とすることから生じた定義である。つまり、一般的にボランティアとは、公的もしくは社会的な活動に自発的に奉仕する人と理解されている。
また、奉仕を意味するという点において、ボランティアは、奉仕を意味するサービスに類似する語でもある(本連載第6回「サービス」参照)。辞書に従うならば、サービスとボランティアの違いは、前者が奉仕の行為を、後者がそうした行為をする人とまとめることができよう。しかし、口語では「ボランティアでやってくれるのですね?」、「ボランティアをしたい人」という表現もよく聞くし、「ボランティア休暇」という制度も存在する。誤用というべきであろうが、日本語で使われているボランティアは名詞として用いられ、行為者だけでなく、行為そのものも表す。
行為と行為者とを混同するという上記の用法が示しているのは、日本語のボランティアにおいては、自由意志が強調されて理解かつ使用されていることであろう。ボランティアは有償であるべきか。中等教育における内申書の評価対象としてボランティアを入れるのか、大学の単位として認定される行為をボランティアと呼べるのかどうか。こうしたボランティアをめぐる近年の議論は、ボランティアが自由意志に基づくべきだという思想の蔓延を示唆している。なぜか。この疑問を解きほぐしてみよう。
 |
志願兵と VAD――仲間への共感 |
確かにボランティアはラテン語を起源とする語ではあるが、各国語の発音を根拠として考えるならば、日本語のボランティアはラテン語ではなく英語を経由して輸入された外来語である。ボランティアを表す主要西洋言語を比較してみると、フランス語では voluntaire(ボロンテール)、イタリア語では volontario(ボロンタリオ)、ドイツ語では Freiwilliger/Freiwillige(フライヴィリガー/フライヴィリゲ)である(池田 175)。もちろん英語の volunteer(ボランティア)も自由意志を含意する語である。しかし、『オクスフォード英語辞典』の名詞 volunteer の項目を見てみると、英語での初期の用法は17世紀半ばで、義務としておこなう者に対して、自発的に軍事業務をおこなう、もしくは、軍事業務に自ら登録する者とある。いわば志願兵を意味する。日本語話者の私たちにとって馴染みのある自発的に奉仕する者の意は、志願兵の用法が登場した後の17世紀後半に登場する。現在の英語の用法においては、後者の意味が一般的ではあるが、前者の意味もさほど珍しい用法ではない。つまり、英語におけるボランティアとは、第一に(傭兵と差異化する意味で)志願兵や義勇兵を意味し、第二に、奉仕する対象が軍にせよ社会にせよ、自発的に何かに奉仕する者という意味を持つ。なお、英語の volunteer には動詞の用法もあるが、日本語では動詞として用いられない。したがって、本論で掘り下げたいのは名詞のボランティアだ。
具体的に考えてみよう。徴兵制がなかった英国が第一次大戦への参戦を決めた時、数多くの若者が志願兵(volunteer)として名乗り出た。開戦して18ヶ月間、自国のために戦おうと志願した若者の数は毎月10万人を超え、その数は300万人に上ったという(Gibson and Ward 6-7)。従軍したのは男たちだけではなかった。軍に労働力を奪われた結果、女たちもまた看護や傷病兵を運ぶ救急車の運転など軍の補助業務に従事することが求められた。そうした女性奉仕団体は複数あるが、なかでも中産階級女性を中心として組織された救急看護奉仕隊(Voluntary Aid Detachment; 通称 VAD)が有名である。VAD がとりわけ有名な理由は、VAD 従軍者の中には大学進学第一世代の女性たちがいて、戦後、作家になった彼女たちがその経験をフィクションやエッセイなどで記したからである。
そのような著作の一つであるヴェラ・ブリテンの自伝的フィクション『若者の証言』(1933)に、彼女のボランティア業務が記録されている。同書はイギリスで同名のタイトルで、1979年にはテレビドラマ化され、2014年にはアリシア・ヴィキャンデル主演で映画化(邦題『戦場からのラブレター』)されたため、イギリスではよく知られている。
VAD としてロンドンの病院で働くことになった23才のブリテンが最初に配属されたのは、外科手術の必要な患者60床を受け持つ病棟だった。そこで彼女は、職業看護婦を補助する形で、医療業務を含めた様々な雑事をこなす。病院で寝起きしながら働く彼女に与えられた部屋は、持参した本の置き場所に困るほど小さく、劣悪な環境での労働だった。5時45分には起床し、「冷え切った部屋で氷のように冷たい水で顔を洗い」、宿舎を朝6時15分に出発しなくてはならなかった。そのため、VAD 従事者の中には肺炎にかかる者もいたという。彼女たちの毎日は過酷であったが、「どんな天気の日でも私たち〔VAD 看護婦〕は、勤務時間になれば清潔かつ元気よく装うことを求められていた」(Brittain 207-208)。このように過酷な労働条件であるが、彼女たちは無償ではなく、年間20ポンドと制服代および制服の洗濯代が支給された有償労働者であった。
ブリテンの従軍理由の一つは、自由への希求であった。戦前の英国中産階級女性は一人で出かけることなど許されず、付き添いが必要だった。加えて、成績優秀で努力家のブリテンがどんなに大学進学を希望しても、父親は意に介さず嫁仕度の一環として高価なピアノを買い与えるだけなのに、学業成績の芳しくない弟には、インドでの公務員になるか家業を継がせるかどちらかを決めるために大学進学を画策する。そうした窮屈かつ不公平な中産階級女性の暮らしにうんざりしていたブリテンが、VAD への従事によって独立の自由を感じたのは当然だっただろう。ただし、志願兵と同様に軍隊の下位組織として運営される VAD 労働者は、軍隊の指揮系統に入るため、実際には自由などない。
ブリテンの事例が示しているのは、ボランティアが従軍という国家への奉仕者を意味しており、また無償とは限らず有償労働でもあり得たことであるが、それよりも重要なのは、彼女の行為が仲間への共感の表明だったことである。フェミニズムに共感してくれる同世代の仲間(恋人、弟、友人たち)らはみな、開戦とほぼ同時に志願兵として従軍した。ブリテンは、そんな彼らのために間接的にであっても役に立ちたいと願い、VAD に入る。そのためには彼女は学業すら中断する。街の人びとから女子が大学に進学するなんて「不自然」かつ「不快極まる」(Brittain 73)と冷たい目で見られ、必死に受験勉強してオクスフォード大学に入学したというのに。彼女は、大学が世間から遮断されているように思えるので持久的な肉体労働に従事したいとすら述べる(Brittain 140)。このように語る彼女が従軍した理由は、独立の自由であるとともに仲間への共感の表明である。いわば、彼女にとってのボランティアとは、自分のフェミニズム思想に共感してくれる仲間への連帯の表明だったのである。
 |
「ボランティア元年」としての関東大震災――セツルと朝鮮人虐殺 |
日本において、今日のように学生を含む市民がボランティアに参加するようになったのは、1995年の阪神淡路大震災の災害支援が契機と言われている。多数のボランティアが全国から集まり、被災者の救援や支援活動をおこなった。兵庫県の推計によれば、地震発生の翌年までに累計137万人がボランティアとして参加し、その後もボランティアが継続的に集まり、1997年12月までに延べ180万人が被災地で活動したという(兵庫県県民生活部生活文化局生活創造課)。そのため1995年は、今日では「ボランティア元年」とも呼ばれる(松本「阪神淡路大震災23年」)。
それよりもはるか以前、ブリテンが VAD に従事して間もない、1923年9月1日の関東大震災後に、セツルメントと呼ばれるボランティア運動が日本にあった。セツルメントとは、宗教家や学生を含む大学人など知識人らが貧困層地域に移り住みながら、地域住民とともに地域の改善をはかる運動である。定住を意味する英語の settlement に由来するセツルメント運動は、サミュエル・バーネットが提唱した運動として知られ、特定の宗教に依拠せず、知識を持った大学人が社会事業の相談員として貧困地域の人びとの友人や隣人のところに移住する一種の社会事業であった(“Samuel Augustus Barnett”)。池田浩士によると、このセツルメント運動はイギリスだけでなく米国などに波及し、社会運動家の片山潜などを経由して日本に紹介された。このセツルメントが大震災のあった年の12月に、東京帝国大学の学生を中心に結成された(通称「帝大セツルメント」もしくは「セツル」)。関東大震災は、池田曰く、阪神淡路大震災に先んじた日本最初の「ボランティア元年」なのである。
東京帝大のセツルメントや阪神大震災後のボランティアに見られるように、災害の後に人びとが助けあう姿は、あたかも新たなコミュニティ形成の予兆のようだ。災害後の人びとの相互支援の現象を、「地獄に建設された天国」と名付けたのはレベッカ・ソルニットである。
同名の著作(邦題『災害ユートピア』)でソルニットは、サンフランシスコ地震、ハリファクス大爆発(貨物船大火災事故)、ロンドン空襲、メキシコシティ大地震、アメリカ同時多発テロ事件、ハリケーン・カトリーナなどの災害後の地域で生まれた人びとの交流やコミュニティを論じる。「災害は一瞬のうちに混乱状態を引き起こすが、そのカオスに放り込まれた人びとはたいてい、爆発事故や地震や大火が起きる以前にあった社会ではなく・・・・・・相互扶助の社会に近い秩序を一時的に作り上げる。それは人びとを解放して、普段より気前が良く、勇敢かつ有能な、本来の自身と理念に回帰させる」(ソルニット『災害ユートピア』137)。
本書を、災害を通じてコミュニティ形成がなされることを示した本だとまとめる論者もいるが、それは正確とは言えない。むしろ本書が示しているのは、20世紀以降、現代にいたる米国が持続的に災害状態におかれていることであり、災害の後の一時的コミュニティ形成よりもその前後に何が起きたか・起きるのかを見極めることの重要性である。2009年に執筆された本書のあとがきで、ソルニットが、史上初のアフリカ系アメリカ人による大統領選の勝利を喜びつつも、同時にリーマンショック後の米国が災害状態にあるとして、オバマ大統領の就任を迎える世界を被災地に例えていることは、その次の大統領を思うならば秀逸である。
災害はわたしたちに別の社会を垣間見させてくれるかもしれない。だが、問題は災害の前や過ぎ去ったあとに、それを利用できるかどうか、そういった要求と可能性を平常時に認識し、実現出来るかどうかだ。ただし、これは将来平常時があればの話である。私たちは今、災害がますますパワフルになり、しかも今までよりはるかに頻繁に起きる時代に突入しようとしている。(ソルニット『災害ユートピア』 431)
本書において強調されるのは、一見するとコミュニティ形成に見えるかもしれないが、むしろ災害ユートピアのその経緯である。災害が常態化しているのだとすると、本書が示唆しているのは、ボランティアによって災害後に形成されたユートピアに希望を見るだけでなく、そのコミュニティ形成を過去から現在までの出来事を未来に連なる形で系譜的に検討する重要性だろう。
今いちど、帝大セツルメントを考えるならば、それは、日本が民主的風潮(大正デモクラシー)から、表現の自由や結社の自由が抑圧されていく時代(昭和ファシズム)への転換期の、大学生と労働者階級との新たなコミュニティ形成の運動であった。それは、百貨店で働く職業婦人、モボやモガなどに代表される、大正デモクラシーと呼ばれるリベラルな思潮の産物だろう。さらにセツルは、そうした都市文化だけでなく、1918年富山の魚津から始まる日本全国の米騒動、1919年の植民地朝鮮での三・一独立運動、1922年の全国水平社の創立などの日本各地における社会運動の系譜に位置づけられる(池田 33-36)。
しかし、大震災はセツルのような社会的なムーブメントをもたらす一方で、横浜、熊谷、秩父、小山など関東全域にわたって起きた朝鮮人虐殺(加藤 参照)という残酷な事件も起こしている。ここで殺害された人びとは、1910年の韓国併合条約によって、戸籍法による違いがあったとしても、「臣民」であるという意味では同じ大日本帝国の一員であったはずだ。セツルの思想とは相容れないように思われる、この虐殺事件を、昭和ファシズムへと向かう過渡期の出来事と捉えることも可能だろうが、人びとがコミュニティ形成をしたいと願う時にこそ、その理想をめぐって緊張関係がもたらされるとも言えるだろう。
帝大セツルが示すように、関東大震災後のボランティアとはコミュニティ創生であった。「ボランティア元年」のセツルと朝鮮人虐殺という二つの自発的な動きが示しているのは、階級としては包摂的、人種としては排他的な動きが同時に起こったことである。人道的には相対立する動きであることは間違いないが、両者は、コミュニティ形成のベクトルが異なる場合、そこに極度に深刻な亀裂を生みだす可能性を示している。
 |
増殖する「ボランティア」――「ふれあい社会」 |
阪神淡路大震災で多くの人びとが自発的に被災者を支援したことは事実だが、行政レベルでのボランティア促進の動きは、それ以前から始まっていた。1993年、厚生省(現厚生労働省)は「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」を発表した。これは、国民の社会福祉への参加を促進するために制定した指針で、福祉活動に対する理解の増進、福祉活動の条件整備、住民参加型福祉サービス供給組織の活動、企業および労働組合の社会貢献活動、地方公共団体における社会福祉に関する活動への参加の促進のための支援が盛り込まれている。いわば、日本各地に広くボランティアを促進する告示である。
そして、阪神淡路大震災の以前から今日にいたるまで、ボランティアの組織化に傾注した一人が、元官僚の堀田力である。公益財団法人さわやか福祉財団の設立者として知られる堀田は、ある世代までには東京地検特捜部検事としてロッキード事件を捜査し、起訴後に田中角栄元首相に論告求刑をした人物として、よく知られている。
堀田の著作『挑戦!――あすなろの夢を追って「ボランティアの世界」を拓く』(2008)によると、彼のさわやか福祉財団の原点は、外務省に出向し、米国ワシントン DC の日本大使館での勤務経験にあるという。堀田は次のように語る。「私が広めようとするボランティアも、〈してあげる〉という気持ちが少しでもあったら、それが態度に表われて、相手の心を傷つける。してもらう方は、ありがたいと思うと同時に、してもらわなければならない自分を悔しいと思っているからである」(堀田 34-35)。このように考える堀田の目標「新しいふれあい社会をつくる」(堀田 35)とは、ボランティアを通じた協働の力によって形成される市民参加型の社会であろう。
「ふれあい社会」の実現のために堀田が提案したことが二つある。第一の「ふれあい切符」(もしくは「ボランティア切符」)は、ボランティア行為者の活動の時間をボランティア団体に預け、将来、本人や家族が必要となった時に、その時間分の援助活動をするという仕組みである。つまり、将来の援助活動者に対する謝礼金に充当するという形の有償のボランティアとすることによって、堀田は、幅広い参加者を募った。堀田の「ふれあい社会」は、ボランティアを贈与の観点から考察する仁平典宏が名付けた〈贈与のパラドックス〉の回避の結果であろう。ボランティアには、称賛/忌避、肯定/否定という両義的な言説が生みだされると仁平は指摘する。ボランティアは、政治的左派からは国家や経済界による動員もしくはやりがい搾取として、政治的右派からは――たとえば2004年のイラクで人道支援をおこなっていた日本人ボランティア人質事件のように――自己欺瞞もしくは偽善者として、批判の対象となってきた(仁平8-9)。左派からは無償労働であることを、右派からは自己満足であることを、批判されていると言い換えてもよいだろう。ボランティアという「他者のための」行為として――仁平曰く「贈与」として――肯定的に捉える人びとは、そこに市場主義化した社会における変革の原理の可能性を読み取る。他者のための行為であるはずのボランティアは、他方で、他者のためどころか、何かを奪っていく行為――反贈与――でもあり得る。そうした反贈与的状態を打開する施策として「ふれあい社会」という形式を堀田は提案していると考えられる。
堀田の第二の提案は、子どものボランティアの拡大である。阪神淡路大震災を契機にボランティアの社会的認知度が上がったことに注目した堀田は、学校教育にボランティア体験学習の導入を推奨する。堀田の構想は、学習としてボランティア体験をさせる授業であるので、自発的な活動ではなく「強制」(堀田 101)のボランティアである。
強制のボランティアとは語義矛盾だが、このような用法が登場したのは阪神淡路大震災後のことであった。1990年代は、ボランティアに関する行政レベルの政策が増加し、また、それに伴って新聞もしくは学術論文などにおいて大いに議論される一方で、2000年代になると言葉そのものが相対的に使われなくなっていったという(仁平 359-362)。
そして、ボランティアに代わって社会運動を表す語として用いられるようになった語が、非営利組織を意味する「NPO(Non Profit Organization)」である(仁平 396-401)。NPO というのも不思議な言葉である。営利(profit)を目的としない組織というが、営利そのものが利潤、利益、得もしくは有用性などを意味する多義語であるため、非常に包括的な語と言って良いだろう。そのため、NPO の活動領域は多岐にわたる。「内閣府 NPO」が紹介する NPO の活動分野には、「保健・医療・福祉」、「国際協力」、「学術・文化・芸術・スポーツ」、「災害救助」、「男女共同参画社会」、「人権・平和」、「子どもの健全育成」などが並ぶ一方で、「情報化社会」、「観光」、「経済活動の活性化」、「科学技術の振興」、「職業能力・雇用機会」などが含まれる。
ボランティア、サービス、NPO、ふれあいなど、他者のための行為を表す言葉は、増殖する一方である。冒頭で言及したボランティアという語が、行為と人の両方の意味を表すことも、この文脈で説明可能であろう。子ども食堂やホームレスへの炊き出し、DV シェルターの提供。これら市民が自発的におこなっている行為や、上記の NPO の活動領域は、無償で市民が担うべきことなのだろうか。これらはどれも(痛ましいことに)慢性的な問題として指摘されているのだから、行政が税金を用いておこなえばよいことであるはずだ。ボランティアの類語の増殖が示しているのは、無料もしくは低賃金で市民に労働を担わせるという新自由主義的思想の拡散である。
では、ボランティアの搾取性が指摘されてもなお、人びとがボランティアを担おうとするのはなぜなのか。金子郁容は市場経済で分断された社会において人との関わりを求めるからだと説明する。現代社会が金融、産業、公共サービス、行政・官僚システムなどの「巨大システム」によって管理・運営されており、私たちには、そのシステムがどのように運営されているかが知り得ない(金子 68)。ボランティアはそうしたシステムから疎外された人びとのネットワークによる抵抗であり、それによってもたらされる関係性は金銭に還元できず、また、経済性の規定する価値観とは異なる多様な価値を提供するのだと金子は言う(金子 199)。
金子のネットワークと堀田の「ふれあい」はともに個人と個人の関係性を強調している。しかし、両者は、新自由主義という巨大システムの抵抗とはたり得ない。むしろ、それを補強する行為である。ボランティアを思考する時、私たちは、金銭に還元できない関係性、ふれあい、ネットワーキングの意味を問うことが求められている。なぜなら、そうした関係性を無批判に求めることは、否応なく私たちを「巨大システム」の支持者にしてしまうからだ。行政がおこなうべき仕事を無料でおこなうことによって、現状の枠組みを継続することに加担してしまうのだから。ふれあいやネットワーキングは、「巨大システム」の有り様から目をそむけては実現しない。
私たちに残された手段は「巨大システム」を継続的に監視し続けることだろう。前述のブリテンは、戦争によって仲間を失い、自由で独立のモメントと信じたボランティアが、実は戦争協力に過ぎないことに気付く。そんな彼女が選んだのは、『若者の証言』という自らの VAD の経験の言語化だ。
私に残された唯一の手段は、私自身の話が、大きな出来事を背景におこった非常によくある物語であることを、できるかぎり誠実に語ることであった。その行為は、個人の物語は私的としておくべきだと信じている人たち全員を不快にさせることだった。(Brittain 12)
『若者の証言』とは、自由を求めた VAD による国家行事である戦闘という「巨大なシステム」の検証の物語なのである。
第一次大戦のイギリス女性の VAD、関東大震災のセツルと朝鮮人虐殺、ふれあい社会という実例が示しているのは、ボランティアには、自由への希求とコミュニティ形成の希求が含まれていることである。ブリテンの『若者の証言』の詳細かつ長大な記述は、その二つの緊張関係を批判的に問い続けることの難しさを示しているのだろう。しかし、その問いを誰かと共有していくことでしか、私たちは、ボランティアを自分たちの文化にすることができないのではないだろうか。
〈参照文献〉
|
松永 典子(まつなが のりこ) 早稲田大学教育学部准教授。専門は20世紀から現代までのイギリス文学・文化およびジェンダー理論などの批評理論。共編著に『終わらないフェミニズム――「働く」女たちの言葉と欲望』(日本ヴァージニア・ウルフ協会・河野真太郎・麻生えりか・秦邦生・松永典子編著)(研究社、2016年)、共訳書に『マクミラン版世界女性人名大辞典』(竹村和子訳監修)(国書刊行会、2005年)など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |