

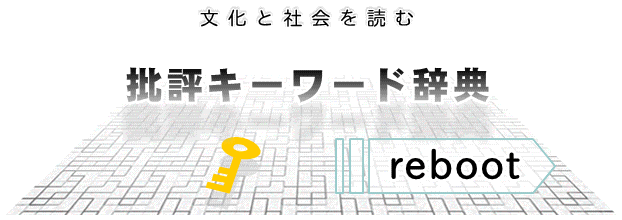
第1回
連載にあたって
2013年に私たちは『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』(研究社)を上梓した。イギリスの批評家・文筆家であるレイモンド・ウィリアムズの『キーワード辞典』(初版1976年)の精神を受け継いで、現在の私たちの社会と生活の変化を色濃く反映する「言葉」についての思索を行ったものである。
『批評キーワード辞典』は、『Web 英語青年』における連載をもとに編集された本である。連載は2010年4月から2012年3月まで、足かけ2年にわたって行われた。この期間を見て気づかれると思うが、連載の半ばには日本社会を揺るがす大事件が起きた。2011年3月11日の東日本大震災と、それが引きおこした福島の原発メルトダウンである。
震災の当日、私(河野)は連載の締め切りに向けて、「自由」というキーワードについての文章を書きはじめていた。震災後の混乱と避難生活(告白するが、私は家族を連れて東京から避難した)のせいもあったが、それ以上にこの社会の大きな変化があまりにも急速に、目の前で起きていたために、それについて考えて書くことは困難を極めた。結局、「自由」は、震災のことは忘れて当初のプラン通りに書くことに徹して、なんとか脱稿することができた(が、今読み返せばそこには震災の痕跡がありありと読み取れる)。
その後の連載は、震災後の社会の変化や、震災が明らかにしてみせた私たちのこれまでの社会のあり方を色濃く反映することになった。とりわけ、「技術」「悲劇」「信じる」といった項目にそれは明らかである。
その震災からすでに8年が経過しようとしている。
この社会はその8年間でひたすらに下り坂を駆け下りてきた。震災の直後には、これまでにない規模の反原発デモが起きるなど、社会の変化について一種多幸症的な期待を抱いたがゆえに、その後の反転はなおさら意気消沈させるものだったと言わねばならない。
しかし、私たちはそうやって意気消沈しつづけているわけにはいかない。もし私たちが短期的な社会の変化の期待に裏切られたなら、裏切ったのは社会の方ではなく、そのような期待を抱いてしまった自分たち自身なのかもしれない。そうなら、私たちは変化についての期待や見通しを、組み立て直さなければならない。
本連載は、そのような経験と意図のもとに、『批評キーワード辞典』を「アップデート」していこうとする試みである。新たな「言葉をめぐる冒険」に乗り出すことで、私たちの社会についてもう一度考え、そして働きかけていきたい。そのような冒険をできるだけ多くの読者が共にしてくださることを願っている。
2019年1月
河野 真太郎
 | ポピュラーな |
「ポピュラーな」というカタカナ言葉には、その元となっている popular という英語と同様に、さまざまな意味がある。基本的な意味は「人気のある」というものだろう。多くの人に知られ、好まれている、という意味だ。それ自体、ふつうは悪い意味では使われないのだろう。だが、場合によっては、人気があることは疑わしく、非難されるべきことだ。例えば「ポピュラー・カルチャー」という言葉を考えてみよう。それは、少数の人たちに限定された高級な文化とは違った、「大衆的で、低俗な」文化という含意を持ちうる。「ポピュラー音楽」は音楽にこだわりを持つ人たち(必ずしもクラシック音楽愛好家である必要はない)にとっては唾棄すべき音楽の別名だ。
それとは逆に、ポピュラー・カルチャーとはすべての人に開かれたすばらしい文化だ、と言うこともできる。この可能性については後段で検討したいが、当面の問題は、ポピュラー・カルチャーという言葉が使われるにあたってそのような意味を込められたり、そのような意味で受けとめられることはあまりないということかもしれない。
それがどうあれ、ポピュラーであることとは人気があることである。この定義に反対する人は多くはないだろう。だが、人気があるとはどういうことか? 今書いているこの文章は、一体何人の人に読まれれば、人気が出たと言えるのか? テレビに出たり、全国紙で文章を書いたりすればその人は人気があると言えるのか? それとも現在であれば、インターネット上の SNS で多くのフォロワーを獲得すれば(たとえテレビなどの既存メディアに出ていなくとも)人気があると言えるのか?
これらの疑問に対する答えがなんであれ、どうやら一つのことは確かなようだ。つまり、程度はともかくとして、人気があるとは多くの人に好まれることだ、ということである。
 |
ポピュリズムと個人主義 |
だが、そのような「ポピュラーな=人気がある」の定義は、現代においては大きな逆説を抱えていることを指摘したい。
人気があるというのは、多くの人の注目を浴びることなのだから、それは集団的なもののはずである。ところが、現代において支配的かもしれない「人気」の本質は、集団的というより個人的なものなのである。
この逆説を示すために、「ポピュラー」と同根の言葉である「ポピュリズム」について考えてみよう。ポピュリズムという言葉には歴史的な変転があって、それ自体詳細な検討を必要としそうであるが、ここではごく簡単にその意味を確認しよう。
『オクスフォード英語辞典』によると、populism という英語の初出は1891年の『ニューヨーク・タイムズ』紙である。同辞典は、この言葉を、「ふつうの人びとの利益を代表しようとする、さまざまな政党の政策もしくは原理」と定義する。これだけだと、ほぼ民主主義の定義と変わりがない。『オクスフォード英語辞典』がカバーしていないのは、「人気取り政治」とでもいった最近のニュアンスであろう。政治家が代表すべき国民や市民の数が純粋に増大し、「大衆化」すると、メディアを通じて分かりやすいメッセージを発して人気取りをすることが政治の重要な技術となる。
ここで問題にしたいのは、この後者の意味でのポピュリズムである。これに関して、そしてとりわけ日本におけるポピュリズムの特徴に関して、小田中直樹は興味深い指摘をしている。小田中によると、近年欧米で盛り上がっている左派ポピュリズムの現象と比較して、日本はポピュリズムといえば右派ポピュリズムしか存在してこなかったという。
それがなぜなのかという問題は脇に置いておいて、ここで注目したいのは日本の右派ポピュリストの特徴についての小田中の指摘である。小田中は、「過去半世紀の代表的なポピュリスト」として橋下徹、石原慎太郎、細川護煕、そして田中角栄の名前を挙げる。そして、これらのポピュリストたちの共通点とは、「異端の存在つまり一匹狼であるか、少なくとも一匹狼というイメージを与えたこと」であると指摘し、「彼ら日本の右派ポピュリストの共通点は「反システム(アンチ・システム)」と要約できる」と述べている。
この議論には説得力がある。どうせなら、細川を挙げるよりは、「自民党をぶっこわす」と言って人気を博した小泉純一郎を挙げた方がよかっただろう。日本の右派ポピュリズムは(そして左派ポピュリズムが存在しないとすれば、あらゆるポピュリズムは)既成の制度を批判し破壊する個人を崇拝するポピュリズムなのだ。人気取り政治という集団的なものが、個人主義を原理としている。現代日本においてはどうやら、人気がある、つまり集団の注目を得るためには魅力的な形で「個人」である必要があるのだ。
この個人と集団の逆説は、政治の水準だけではなく、例えば「自分らしさ」の言説にも言えることかもしれない。「自分らしさ」は現代日本ではそれ自体が商品化され、みなは「かけがえのない自分」になるために他の人たちと同じものを買う。「個人であれ」という集団的な命令。
 |
シャカイ系と人気 |
日本における「人気」とは、ずっとそのようなものだったのだろうか。たしかに、それを例えば判官贔屓という日本の伝統的な心性で説明することも可能かもしれない。
ここでは、そうではなく、上記のような逆説の歴史は意外と短いのではないかという仮説を検証してみたい。
河野真太郎は――とは、本稿を書いている本人なので、私は――『戦う姫、働く少女』(第4章)において、「シャカイ系」という物語類型を論じている。シャカイ系は、「セカイ系」のもじりである。セカイ系とは、『新世紀エヴァンゲリオン』などを典型とする、1990年代から2000年代に流行した(そして現在でも流行、というより多くの物語のほとんど無意識になっている)物語形式であり、そこでは主人公とその恋愛対象の「僕と君」の関係性が、なんの媒介もなく世界の終わりといった問題に直結する。なんの媒介もない、というのは、世界の危機や終わりといった問題であれば必然的に出てくるはずの、「僕と君」関係の外側の社会が存在しないということだ。
私は、セカイ系が流行した一方で、じつは社会を過剰に描く物語類型も同時に存在してきたことを指摘し、それをシャカイ系と名づけた。その典型的な作品は、『踊る大捜査線』(1997年)であり、『ドクター X 〜 外科医・大門未知子 〜』(2012年〜)である。
シャカイ系は、社会を描くゆえにセカイ系よりリアリズム的ですばらしい、というわけではない。シャカイ系は、社会を描くことによってむしろそこで描かれたもの以外の社会を抑圧するという意味で、より問題含みなのである。その場合に描かれる社会とは何か。『踊る大捜査線』であればそれは非効率な警察官僚組織である。主人公の青島刑事の有名な台詞「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ!」は、それをみごとに表現したマニフェストである。会議室に象徴される官僚組織は、現場の現実に対応できない。青島刑事はそのように非効率な官僚組織に対抗する個人だ。『ドクター X』の主人公であるフリーの天才外科医大門未知子も同様だ。この場合、主人公が痛快に批判するのは巨大で腐敗した病院組織である。まさに、小田中の言う右派ポピュリズム政治家の人物類型そのものだ。
私はシャカイ系を具体的な歴史的文脈の産物として論じた。それは、新自由主義である。新自由主義はそれに先行する福祉国家を、官僚制度にがんじがらめにされた時代として批判し、国家と官僚の規制を取りのぞいて市場の自由を最大化することがさまざまな問題を解決するのだと主張する。そして新自由主義は単なる経済理論ではない。私たちの人生や生活を支配する、まさにイデオロギーなのである。そのイデオロギーの中心には個人の崇拝がある。新自由主義は個人の自由を約束し、それがよりよき社会をもたらすことを約束する。
逆に、官僚制度に対するヒロイックな個人の活躍を描く『踊る大捜査線』や『ドクター X』は、基本的には新自由主義的な「民営化」の思想を喧伝しているということになる。青島刑事が元は民間企業で敏腕営業マンだったことは無意味ではない。
だがここには、ポピュリズムに見たのと同じ逆説が待ち構えている。つまり、新自由主義は個人主義を崇拝するけれども、その崇拝という行為においては非常に画一的で集団主義的なのである。個人の自由を約束する新自由主義が、常に権威主義的な国家によって促進されてきたことには、その意味でなんの矛盾もない。
そのような、隠された集団主義の命令によって、別の集団性が破壊されてきた。つまり、市場における個人たちの競争の妨げとなるような別の集団性である。端的に言ってそれは例えば労働組合であり、フェミニズムの一部が目指していたはずの女性同士の連帯だ。
 |
ネットワーク型の集団性? |
ここまで述べたことが正しいなら、そしてそれが「ポピュラーな」という言葉についての私たちの社会的な想像力のありさまを正しく表現しているなら、そこからの出口はどこにあるのだろうか?
ひとつにはここまで述べた個人と集団の逆説を否定することなく、新たな集団を構想しようという方向があり得るし、実際に多くの論者はその方向を追求してきた。例えば『〈帝国〉』を書いたマイケル・ハートとアントニオ・ネグリの言う「マルティテュード」がそうであるし、日本では東浩紀(『一般意志 2.0』『弱いつながり』『ゲンロン 0 観光客の哲学』)が、ネットワーク的な、もしくは中心性や所属に基づかない連帯の形を探究している(これらについては『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』の「みんな」の項目も参照)。
こういった議論は、「個人」を否定することなく、というより新自由主義的な個人は消し去れない前提として、そこからどうやって新たな集団性を作りあげるかを真摯に問うものであるのは確かだ。だが、それが上記のような右派ポピュリズムに実効的に対抗できるのかどうかは、にわかには判断しがたい。
というのも、じつのところ、これらネットワーク論者は、私のここまでの議論と同じ弱点を共有しているからだ。それは、「歴史的スパンの取り方」に関わる。
ハートとネグリの議論を例に取ろう。彼らのマルティテュードの議論は、現在が新たな〈帝国〉の時代であるという認識に基づいている。大雑把に言って〈帝国〉とは国民国家を単位や中心としない、グローバルに広がった権力のあり方のことである。だがそれは、単に「上からの」権力であるだけではない、それはそれ自身を「構成する」権力、つまりグローバルなプロレタリアートに依存するものなのである。ネットワーク型の権力の裏側にぴったりと張り付くような形で展開されたネットワーク型の労働者階級、それがマルティテュードなのだ。 ここで考え直してみたいのは、私たちは本当にそのような新たな時代に生きているのだろうか、ということだ。つまり、ネットワーク型権力/「個人」を原理とする集団主義は、グローバリゼーションであれ新自由主義であれ、私たちの時代に生じた新たなるものなのだろうか。
 |
ブルームズベリー分派と社会主義下の人間の魂 |
実のところ、現代におけるネットワーク型権力の勃興的な形態は、「民衆社会」とその中での民主主義と同じくらい古い歴史を持っている。これについて参考になるのは、レイモンド・ウィリアムズ「ブルームズベリー分派」というエッセイである。
ブルームズベリー分派もしくはブルームズベリー・グループとは、ヴァージニア・ウルフ、ジョン・メイナード・ケインズ、E. M. フォースターらを含む、20世紀前半のロンドンはブルームズベリー地区(中・上流階級の居住区)で生じた文化集団の総称である。
ウィリアムズはブルームズベリー・グループを、イギリスの上流階級に伝統的に生じてきた「分派」の最新版として論じる。分派とはつまり、上流階級の中に生じる一種の前衛であり、支配的な価値観に一見反抗しながら、次の新たな支配的価値観を生み出すような(ウィリアムズの別の著作で有名になった言葉では「勃興的」な)グループのことである。
だがウィリアムズは、ブルームズベリー・グループを過去の「分派」(ゴドウィン・グループやラファエル前派)と比較して独特のものと見る。その独特さとは、ブルームズベリー・グループが、自らがグループであることを否定し、グループを束ねる「共通の……理論ないしシステム」を否定したことである(139頁)。だが、ウィリアムズによれば、ブルームズベリー・グループを束ねる理論は存在する。それは、ブルームズベリー・グループが「際立って自由な個人という観念からなる集団」だということだ(146頁)。
ここには、ネットワーク型権力の勃興的な形態が見て取れる。なにしろ集団性を否定しながら、「集団性を否定する」という原理によって密かな集団性を立ち上げているのだから。
実際ウィリアムズは、戦前のこの勃興的な形態が、「その後イングランド文化のあらゆる局面に……浸透してしまった」と述べる(146頁)。「個人を原理とする集団」=ネットワーク型権力は、戦後に自然化していく。ブルームズベリー・グループはその後自然化する=支配的になる個人主義の勃興的形態を、その逆説的な統合原理としていたのだ。
個人を原理とする集団という理念は、さらにさかのぼることができる。『ドリアン・グレイの肖像』などで有名なアイルランド出身の文学者オスカー・ワイルドは、1891年に出版した評論「社会主義下の人間の魂」で、社会主義と私有財産撤廃を擁護している。ところが、逆説的にも、彼が社会主義を擁護する根拠は、それが「個人主義にむすびつく」からである(1175頁)。理想的な社会主義の下では、その構成員はもはや貧困を恐れる必要がなく、私有財産制度がもたらす、競争的で間違った個人主義ではない真の個人主義が実現されるというのである。そのためには、「権威主義的な社会主義」ではだめである(1177頁)。そうではなく「あらゆる結合(association)は完全に自由意志に基づくものでなければならない」(同)。ここでワイルドがアソシエーションという言葉を使っていることは注目に値する。アソシエーションといえば、もう覚えている人も少ないと思うが、柄谷行人が NAM という運動体を2000年に立ち上げた際の集団原理であった。NAM とは The New Association Movement の略である。ワイルドは、現代のネットワーク論者たちの議論を先取りしていた。
ワイルドやネットワーク論者の議論は、戦後に「自然化」したブルームズベリー・グループ的な個人主義――個人を原理とした隠された集団主義――の、意識的批判にはなり得る。だが、両者には一種の性急さが共有されているようである。ネットワーク論者は、自分たちが完全に新たな(ネットワーク的権力の)時代を生きていると考え、それがここまで述べたような長い系譜を持っていることを忘れることによって、そしてワイルドの場合は理想的な社会主義が社会的問題をすべて解決してくれるという一種の技術信仰によって(現代の、AI がすべての問題を解決してくれる、というような議論を彷彿とさせる)。
そのような性急さは、いっぽうではユートピア的な衝動の特徴である。だが、そのような性急な変化への欲望は、新自由主義的な「改革/革命」への衝動と区別がつかない。私たちは、そのような性急さが何を生み出すかをいやというほど見てきたのではないか?
 |
ポピュラー・カルチャーから共通文化へ |
では、そのような性急さから逃れつつ、個人と集団の逆説について考える方法は何であろうか? 最後に、冒頭に示唆したポピュラー・カルチャーについてもう一度考えてみよう。
ポピュラー・カルチャーを、あらゆる人に開かれた平等な文化として肯定的に評価することは可能だろうか。もちろん、原理的には可能である。だが、ポピュラー・カルチャーと呼ばれるものの現状を考えると、全面的にそれが可能であるとは言えない。それは、商業化された文化であり、それを享受し消費する人たちが、何らかの共有のもの(集団的なもの)としてそれをとらえているとは、必ずしも言えない。それはタコツボに入った個人によって消費される。おそらく現在のポピュラー・カルチャーにも、「人気」をめぐる個人と集団の逆説があてはまってしまうのだろう。
そのような文化とはかなり異質な文化の理念を説いたのが、ふたたび、レイモンド・ウィリアムズであり、その「共通文化」の理念であった。ウィリアムズは共通文化を以下のように定義している。
ある現存する経験の一部分がある個別具体的な方法で分節化され、たんにそのほかの人びとへと拡張され――そして教えられ――、その結果ほかの人びとが共有物として所有するようなことがあれば、それは共通文化[コモン・カルチャー]とはならない(共有された文化[カルチャー・イン・コモン]と呼ぶことは可能であるにしても)。というのも、最初に強調したことの必然的帰結とは、ある人民の文化とはすべての構成員がその生活の活動において創造にあずかるようなものでしかありえないということであり、共通文化とは少数派が考え信じることを全般的に拡張したものではなく、人民全体が意味や価値の創造と表明に参加し、またそれにつづいてある意味を選びとり、ある価値を選びとる行為に参加できるような状況の創造にほかならないからだ。(「共通文化の理念」71頁)
ここでウィリアムズが言う「状況」とは、一言で言えば民主主義にほかならない。そうすると、このような共通文化の定義は、ここまで述べたような問題の解決というよりは問題の再提示に過ぎないのではないか、と思われるだろうか。「ポピュラーなもの」をめぐる苦境は、民主主義そのものの苦境にほかならないのだから。また、読み方によっては、ウィリアムズの議論は例えばワイルドの議論と同じくらいに性急なものに見えるかもしれない。
だが、ウィリアムズとワイルドの異質性は決定的である。ウィリアムズは、民主主義が社会的技術として上から与えられ、それによって共通文化が生み出される、といった議論はしていない。引用の最後の一文は字義通りに読まれるべきだ。「共通文化とは……ような状況の創造にほかならない」。ウィリアムズは、民主主義が共通文化を生み出すとは述べていない。むしろ、共通文化とは民主主義の創造の行為、創造のプロセスの別名なのである。
共通文化という理念は、分かりにくい。どれが共通文化で、どれがそうではない、といった発想をすると、とたんに視界がぼやけてしまう。それは、共通文化が何らかの静態的な実態ではなく、上記のようなプロセスの名前だからだ。それはカントの言葉を使うなら統整的理念としてとらえられるべきだ。言い換えれば、「いまだ来たらざるもの」としてとらえるべきなのだ。そうとらえるとき、ウィリアムズの言う「すべての構成員」は、文字どおりに読まれることになる。ある人民のすべての構成員とは、前もって確定された範囲の人びとではない。それは決して排除をともなわないという意味での「すべて」なのである。
だとすれば、「共通文化」に終わりはない。それは常に拡張しつづける。誤解を恐れずに言えば、無限に「多くの人たち」へと拡張しつづける、という意味で、無限にポピュラーなものなのである。
「ポピュラー」の語源には people がある(people と popular はラテン語の populus に由来する)。ポピュラーという言葉を意味ある形で取り戻すとは、この people という意味と価値を取り戻すことであるし、それはウィリアムズの言う共通文化の終わりなきプロセスを発動することである。それは、個人主義によって集団性を隠蔽するのではなく、マルクスが『経済学批判要綱』で述べた意味で、個人を可能にする集団を構想し直すことである。
人間は、社会の中だけで自己を個別化することのできる動物である。 (27頁)
人間は、個人になることによって社会を作るのではない。社会をつくることによってのみ個人たりうるのだ。そしてそれをつくるプロセスは、避けようもなく長い。
〈引用文献〉
|
河野真太郎(こうの しんたろう) 一橋大学大学院経営管理研究科准教授。専門はイギリスの文化と社会、新自由主義と文化。著書に『戦う姫、働く少女』(堀之内出版、2017年)など。共編著に『愛と戦いのイギリス文化史――1951-2010年』(慶応義塾大学出版会、2011年)など。訳書にレイモンド・ウィリアムズ『共通文化にむけて――文化研究I』(共訳、みすず書房、2013年)『想像力の時制――文化研究II』(共訳、みすず書房、2016年)など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |