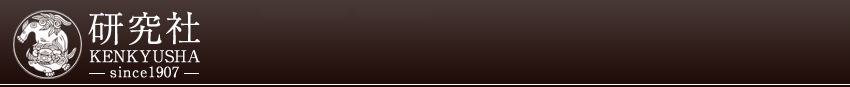

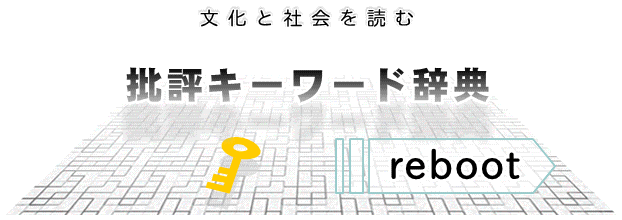
第2回
 | エコ |
「エコロジー」でも「エコノミー」でもない、「エコ」という言葉が日本語で一般に使われるようになったのがいつなのか、どうもはっきりしない。「エコロジー」と「エコノミー」それぞれ別個に考えるのであれば基本的にはどちらも外来語としての出自を持つのだから、それぞれ日本語の語彙として翻訳語なりカタカナ表記なりで定着した時期を特定することはそれほど難しくない。あるいはそれぞれその思想の源流となるものを探って、たとえば「エコロジー」であれば宮沢賢治を現在にまでつながる日本的なエコロジー思想の始祖と位置付けることもできるだろうし、「エコノミー」が経済、つまりは経世済民に置き換えられるとするのであれば、これもまたかなり古い時代まで辿りつつ、それが economy の翻訳語として定着していく過程を追うこともできる。
だがここで考えたいのは「エコ」だ。似た語をダジャレでつなげたいわけではない。実はこの二つの語、歴史をさかのぼるとどちらも古代ギリシャ語で「家」を意味する「オイコス」にたどり着く。しかもこの「家」は佐々木雄大によると、現在の用法とは異なり「家族だけでなく、奴隷、家畜、そして農作業の一切を含む、大きな家族による生産的共同体」を意味していたらしい。語源から考えれば兄弟とも言えるこの二つの異なった語を不思議な形で再結合させたかに見えるのが、現在のわたしたちが日常で使う「エコ」だ。たとえば「エコタイヤ」というときの「エコ」は、低燃費であるという意味で「エコノミー」であり、その結果排出ガスが少なくなり環境負荷が低くなるという意味では「エコロジー」なのだから、「エコ」なのだ。とはいえ、どちらの語も複雑な用法とその歴史的変遷を持っているので、事態はもっと複雑だ。ここでは、望み薄い語源的なアプローチにこだわらず、そこに託されている思想や願望の水準の感情をときほぐしていこう。重要な語を紐解くことで社会を読み解くカギとするというよりは、社会の多層的な感情が流れ込む形で鋳造された鍵語として。
 |
「エコ」を支えるもの |
現在の「エコ」につながるもっともはっきりとした源流の一つとして、1989年から開始された「エコマーク」が挙げられる。エコマークは商品やサービスの環境負荷を第三者機関が認証する、タイプ I 環境ラベルと呼ばれる日本で唯一の事業だ。これは平たく言えば商品やサービスの生産・流通・消費・廃棄において環境負荷の低減を目指す取り組みと位置付けられるものであり、そういった意味で上述した現在の「エコ」のイメージにかなり近い。生産や消費の削減ではなく、むしろ技術の進歩によって可能となるより良い生産と消費の推進を通じて環境問題へアプローチする、というわけだ。この方向性はこれ以降さらに強化される。2000年には循環型社会形成推進基本法が定められ、メーカーなど生産者の責任範囲を拡大する形で包括的なリサイクル推進が法的に整備されるが、これは必ずしも生産や消費を抑制するものではなかった。また、現在のエコカー減税につながる自動車のグリーン化が行われ始めたのもこのころだが、これもまた新技術を用いた自動車への買い替えのインセンティブを高めるという意味で、むしろ消費拡大を通じた景気刺激策という側面が強いものだった。
ここまでくれば、(少なくとも1989年以降の)行政的なレベルで用いられる「エコ」には最新技術への強い信があることが見えてくる。ここで「信」と書いたのは、この感情の内実が社会のそれぞれの立ち位置によって微妙に異なっているからだ。要するに、有権者から選挙という形で「信」を受けた行政と立法が、生産者(メーカー)の技術に「信」を置き、その有権者たちが生産者に「信」をおきつつ消費するといった連続的な構造があるのだ。この「信」の連鎖を支えているのが必ずしも科学的知識による裏付けなのではなく、また別の「信」でしかない、という点に注意したい。極端に言えば「エコ」を支えているのは「盲信」に、あるいはもっと言えばイデオロギーに過ぎないのかもしれないのだ。
ここで、いったん立ち止まって、科学技術と信念あるいはイデオロギーの関係を簡単に整理しておこう。技術とイデオロギーを、あるいは科学と信念を二項対立ではなく相互に近しいものと位置付ける議論は、「エコ」に限定しない形で既刊となっている本連載シリーズ『文化と社会を読む――批評のキーワード辞典』の「信じる」あるいは「原子力」において行われている。たとえば、信号機のついた横断歩道を渡るという日常的行為を考えてみよう。「この道路の横断が100%安全だとは言い切れない」ことをわたしたちは「知って」いるが、同時に「でも経験上、赤信号で突っ込んでくる車はないだろう」と「信じて」もいる。知識と信念は対立的なものではなく、むしろわたしたちの思考や行為の選択において相補的に作用しているものなのだ。くわしい議論は先の『キーワード辞典』をご覧いただくとして簡易的にその結論だけを概観するのであれば、科学と信念は本来相補的であるにもかかわらず、わたしたちはいまそれらが完全に分離した社会に生きている、だから必要なのは「信じる」ことへの信を取り戻すことだ、となる。本論の関心対象である「エコ」に引き付ければ、科学技術は圧倒的優位に置かれ、それを信念あるいはイデオロギーの連続が支えている、となろう。素人にはその一端すら理解するのが難しい科学技術に対して、わたしたちの多くは白旗を揚げて盲信してしまっている。もしそうだとすれば、行うべきは「そんなのはイデオロギーに過ぎない!」と喝破することではなく、あるいは「みんなが科学技術を学ぼう」という非現実的なスローガンでもなく、そこに表されている願望や感情をときほぐし、その内実から「信じることへの信」を取り戻す条件を探ることだろう。では、このエコノミーとエコロジーが短絡してしまっている「エコ」にはどういった感情があり、そこにはどういった「信」の可能性とその条件を見出すことができるのだろうか。
 |
「自然」と欲望の克服:『寄生獣』(1988〜1989、1990〜1995) |
信じるという感情は選択的だ。「Aを信じる」ということは、つまりは「非Aを信じない」という感情と背中合わせになっている。エコマーク事業が開始された当時連載が始まったばかりの岩明均『寄生獣』は、まさにこの「信じる/信じない」についての物語であった。
1988年に『モーニングオープン増刊』(F号)からスタートして三話の中編作品として発表されたあと、『寄生獣』は舞台を『月刊アフタヌーン』に移し、1995年まで連載される。足掛け七年にも及ぶ連載のなかで物語は深まりを見せるが、ここでは89年当時の感情を切り取るために、まずは最初の中編作品としての物語を見てみよう。
主人公の泉新一は郊外に暮らす普通の高校生だが、ある日、どこからともなくやってきた奇妙な寄生生物(パラサイト)に右腕を乗っ取られてしまう。驚異的な学習能力で日本語をマスターしたこのパラサイトは自らをミギーと名乗る。だがこのパラサイトは本来であれば脳に寄生し、首から上の部分すべてを乗っ取り、人間を擬態しながら他の人間を食欲にまかせて捕食する恐ろしい存在だった。脳の乗っ取りに成功したミギーの「仲間」たちの捕食行動により世間は大騒ぎとなるが、知能だけ高くなったが社会性がまったくないミギーに振り回されながら、泉の奇妙な日常が始まっていく … 。
人語を完璧に解しながらも他者への共感を微塵も持ち合わせていないミギーと普通の高校生である泉との会話は、人間中心主義的な生命観を痛烈に批判するものであり、パラサイトのショッキングな捕食行動の描写も相まって大きな話題となった。だがそれ以上に注目すべきはその冒頭部分だろう。連載の冒頭は、正体のはっきりとしない語り手によるナレーションから始まる。宇宙から見た地球を背景に、その声は次のように述べる。
地球上の誰かがふと思った。『人間の数が半分になったらいくつの森が焼かれずにすむだろうか … 』。『人間の数が100分の1になったらたれ流される毒も100分の1になるのだろうか。』誰かがふと思った。『生物(みんな)の未来を守らねば … 』(『寄生獣』第一巻、2, 3頁)。
人口増加が環境破壊と汚染に直接つながれ、人口削減が環境負荷低減に直結することを単純化しつつも明示的に表すこの冒頭のメッセージは、そのままパラサイトという存在の紹介にもなっている。パラサイトはまさしくこの人口削減を行う役割として使わされたものなのだ。要するに、文明とはすなわち人口増加であり、その解決は為され得ないのだから、人間への信をまったく排除した形で「生物(みんな)の未来」を守るためには、人間の物理的な排除しかない、というわけだ。
ここでの、人口爆発を避け難い危機的な問題と見做す態度で想起すべきは、トマス・マルサスの『人口論』(1798)だろう。マルサスによれば、人口は等比級数的に激増していくにもかかわらず、それを養う穀物生産は等差級数的にしか増加し得ない、よって人類は早晩、飢餓に陥ることになる。この見通しが正しいかどうかは別として、この人口増加に対してマルサスが挙げた対策が人口抑制であったことがここでは重要だ。彼は、階級的な下降を恐れて結婚・出産を思いとどまるという「事前予防的な抑制」と、社会の下層階級における急速な人口増加の原因を無分別な救済策に求めた上でその削減あるいは撤廃を通じて行われる「積極的な抑制」を提示している。ここで重要なのは介入主義的な後者の「積極的な抑制」だ。『寄生獣』はこのマルサス主義を引きつぎながら、マルサス以上に積極的かつ極端な解決策を物語装置として用いている。その解決策こそがパラサイトだ。主人公の泉新一は、作中で動物を飛び越えて「昆虫」とも形容される超自然的存在のミギーと対話しながら、物事の認識の大きな差異に戸惑いつつ、人間とパラサイトのハイブリッドとして生きていくのだ。
さて、90年に連載が再開される『寄生獣』はその後どうなっていくのだろうか。様々なエピソードや物語的仕掛けがちりばめられた本作の魅力を詳らかにすることができないのは残念だが、ここではこのパラサイトのその後の運命を追いかけてみたい。それを考える上でもっとも重要なのは、連載再開後すぐに登場し、物語終盤まで最重要人物であり続けた「田宮良子」と名乗るパラサイトだ。彼女はパラサイトでありながらも教員として主人公泉の高校に赴任してくる特殊な存在で、「わたしたちはいったい何なの? [ … ] こんな生物ってある?」と自身の存在そのものを問い続けている。彼女を含むすべてのパラサイトには「この種を食い殺せ」という声が聞こえているとされているが、彼女はその声に逆らい、人間と同じ「普通の」食事をするという実験を行いながら、この声に従わなくても生きていけることを証明する。そのうえで、人間の人口抑制にしかなっていない自分たちの存在の謎を解き明かそうとしているのだ。パラサイトの一種であるミギーは「田宮」との接触に刺激され、泉との対話のなかでパラサイトとの共存の可能性を繰り返し説くが、泉は「あんなやつら信じられるか」と突っぱね続ける。信じられないのだ。「声」は明らかに人間による解決を信じていないが、人間も恐ろしい殺人鬼であるパラサイトを信じられないのだ。
ではその「声」とは誰(あるいは何)なのだろうか。作中ではパラサイトによる「殺人」が「生物(みんな)」の目から見れば「食事」でしかない点が繰り返し確認され、その捕食を駆動する抗い難い欲望を喚起するこの声も繰り返し描写される。2015年に公開された実写映画『寄生獣 完結編』ではそれが人間からの呼びかけとされているが、原作であるマンガ冒頭のあのナレーションを思い起こせば、この声はナレーション内の「誰か」のものであり、少なくとも人間ではないことは明らかだ。では誰の声なのか、誰の呼びかけなのか。これを考えるために、少々迂遠ではあるが、もう一度マルサスにご登場願おう。
マルサスは大幅な加筆と改訂を行った『人口論』の第二版(1803年)において、救貧法批判を通じた「積極的な抑制」の必要性を次のように描写している。
自然の偉大な饗宴には彼[筆者注:親からの扶養を期待できない子ども]の席はない。彼女[筆者注:自然]は彼に立ち去るように告げ、もし彼が饗宴の同席者からの慈悲を得られなければ、すみやかに自身の命令を達成することとなるだろう。もし同席者らが立ち上がり席を空けてやると、別の侵入者が即座にやってきて、同様の寛大な処置を求めることになる。 [ … ] 饗宴の秩序と調和はかき乱され、当初は行き渡っていた豊かさは欠乏へと変わる。 [ … ] 遅きに失しながらも、同席者たちはこの饗宴の偉大な女主人による、乱入者すべてに対するきっぱりとした命令から学ぶこととなる。彼女は来席者全員が豊かさを手にすべきだと望み、無制限な提供が不可能であることを理解し、テーブルが満員の際には新しい参加者を認めることはできないと慈悲深くも拒絶したのだ、と。(471)
救貧法を社会的な法則と位置付けたうえで、マルサスは「彼女の命令」すなわち自然の法の優位を主張している。
『寄生獣』冒頭のナレーションの懸念は、まさしくこの饗宴のテーブルが定員を超えてしまったとの認識からくるものだと考えられる。本作がマルサス主義の延長に環境の危機を描く物語だとすると、パラサイトに聞こえてくる「声」は「彼女の命令」だと言えるだろう。だとすると、「田宮」の思想と行為はただ欲望(食欲)に抗うというだけでなく、「彼女」に抵抗し、「彼女」を克服しようとするものとなる。「田宮」は作中で実験として妊娠し人間の子どもを出産する。そして最終的にはこの「親からの扶養を期待できない子ども」を自己犠牲的な形で泉に託して死んでしまう。死に際に生への執着をまったく見せずこの子どもを他人である泉に託す「田宮」の行為は、「彼女の命令」に徹底的に抗するものであり、その姿は自己生存以上の優先事項を持たないはずのパラサイトが(ここでは泉への)「信」を手にしたものと考えられる。自身の存在理由の謎の解明は、自然が呼びかける欲望の克服においてしか可能となり得ず、それは自己保存という究極の欲望さえも超越するもの、とも読み得る。「田宮」の泉への信頼は彼女自身の自然の克服から導き出されたものであり、物語の末尾では他のパラサイトが「田宮」化していくこと、つまりは自然なる欲望を克服して人間社会に順応していったことが示唆されている。「自然の饗宴」の「女主人」の代理人として登場した「田宮」をはじめとするパラサイトは、「女主人」の命令に背き、欲望を克服し、パラサイトにとっての環境(人間を含む)との共存を目指し、ほとんど実現したのだ。もちろんこれは連載冒頭に挙げられた「誰か」の懸念を払拭することにはならないのだが、この自然なる欲望の克服が本作の中心的モチーフであるとするならば、その筋道は示されたと言っていいだろう。すなわち、欲望の克服と、その延長線上に想像され得る「信」、そして共存だ。
エコマーク事業の開始とほとんど軌を一にした『寄生獣』は、技術的解決を「信じない」ことを、あるいはその機能不全を前提にしつつも、最終的には、解決の糸口として個々人の信を見出そうとしている。とはいえこれは「自然」の遣わしたパラサイトの変化と順応を前提としたもので、人間側はどうかと言えば、結局はこれまでと変わらないのだから、振出しに戻ったともいえるだろう。端的に言って、主人公泉に代表される人間側は、その生活態度全般に関して言えば何一つ変わっていない。はたしてこれで「生物(みんな)の未来」を守ることができるのだろうか。じっさい、生活態度を改めず思想の変化のみで終わりとするというのは環境問題を背景とした作品としては少々物足りない気もする。だが他方で、詳細を知り得ない技術への盲信を安易に持ち上げないという意味では誠実なものとなっていると言えるだろうし、環境問題解決の糸口が個々人の欲望の克服であるというモチーフは、たとえ非現実的ではあっても、いやだからこそ、作品の願望を強く表していると考えられるのだ。
 |
コモンな(みんなの)オイコスにむけて |
『寄生獣』は「エコ」隆盛の始まりの時期にあって、技術的解決の不可能性を物語の条件としながらも、欲望の克服や信の回復への強い願望を描き出した。もちろん思想的転換でしかないこの結論が環境問題に直接介入できるものではないことは明らかだが、それでも別様の技術的解決に飛びつくのではなく、生活の在り方や世界のとらえ方の変化の兆しとなり得る思想的展開に信を置くこの物語の提示している希望は重要だろう。現行の「エコ」が技術的解決を信じて疑わないイデオロギーに支えられているとするなら、そしてわたしたちの多くがうすうす気付いているようにこの「エコ」が問題解決に十分には寄与していないのだとすれば、そこに介入するには別様の思想が必要だ。マルサス主義的な悲観の残滓から始まった『寄生獣』は、こういった思想の粗削りではあるが原石を取り出して見せたのだ。
最後に、この思想の、つまりは「信」の在り方を検討しておきたい。だが、そういえばパラサイトたちは共存の道を選んだのだったが、ミギーはどうなったのだろうか。主人公泉新一の右手に寄生していたミギーは物語の終盤、不思議な形で「お別れに」くる。泉の夢のなかでミギーは普段とはかけ離れた姿で現れ、泉にお別れを告げるのだ。ミギーによれば物語内の戦闘などでミギーの体質が変化したこともあり、外から入ってくる情報をシャットアウトして深い「眠り」につきたいのだという。つまり泉の右手はもとに戻り、パラサイトがやってくる前と変わらない生活が返ってくるのだ、と。すでにミギーと深い絆で結ばれていた泉はこれに強く反発するが、ミギーは次のような言葉を残し、夢のなかから消えていってしまう。
つまりそういうことなのさ … お互い理解しあえるのはほとんど「点」なんだよ。同じ構造の脳を持つはずの人間どうしでさえたとえば魂を交換できたとしたらそれぞれ想像を絶する世界が見え、聞こえるはずだ。 [ … ] きみなら大丈夫 … それより交通事故に気をつけろ。(第十巻162頁)
泉はミギーを理解できていると感じていたがそれは「点」にしか過ぎないし、まったく同じことが人間同士にも言えるとミギーは言っているわけだが、お別れの言葉とするにはなんともかみ合わないセリフだ。だがミギーは煙に巻こうとしたわけではない。他者理解の困難さを述べてはいるものの、だからこそかえって「点」でつながっていることが強調される。不可能ではないのだ。これこそが「信」だろう。さきほど『寄生獣』は「信じる/信じない」の物語だと述べたが、修正しよう。『寄生獣』は「信じない」ことからはじめて「信じる」という可能性を獲得する物語なのだ、と。同じエピソードの末尾で泉は愛する女性とともに、ミギーやパラサイトたち思い浮かべながらこう呟く。「みんな地球(ここ)で生まれてきたんだろう? そして何かに寄り添い生きた … 」。
人間への不信に満ちた「自然の饗宴」の「女主人」の「声」から始まった『寄生獣』は、最終的には「信じること」への希望を、願望を提出している。ではここでの「信」とはなんだろうか。「女主人」は人間も人間による技術的解決も信じていない。彼女の懸念は相変わらず払拭されておらず、技術的解決は見出される気配はない。だがここで考えてみよう。彼女の不信の根拠となっている技術的解決とはそもそも一体なんなのか。
ここで三度、マルサス主義を呼び出してみよう。だがこんど登場してもらうのは、マルサス本人ではなく、彼の人口問題に関する悲観主義と不信を受け継ぎ、1968年に「コモンズの悲劇」で大きな議論を巻き起こしたギャレット・ハーディンだ。ハーディンは技術的解決を「自然科学のみに変化を求め、人々の価値観や道徳観念にほとんどあるいはまったく変化を求めないもの」(1243)と定義付けたうえで、人口問題をそういった技術的解決不可能な問題の一つと位置付ける。彼にとって人口問題とは個人が子どもを残す生殖(breed)の権利あるいは自由を好き勝手に行使することの帰結としてあるのだ。これをハーディンは所有者のはっきりしないコモンズ(共有地、入会地)が個人的利害の最大化をもくろむ人々に搾取される姿に重ね合わせ、その状況を「コモンズの悲劇」と呼んだ。このことから、人口問題にせよコモンズにせよ、その解決は技術的になされるのではなく、自由の制限に求められることになる。すなわち、ハーディンの言葉を借りれば、「生殖のコモンズの放棄」だ。ハーディンにとって自由の対象とはコモンズに他ならず、それは強欲とタダ乗りに搾取されるだけなのだからその制限以外に解決方法はない、というわけだ。
だが本当だろうか。ハーディンの提示したコモンズ観についてはすでに多くの批判がなされている。実際のコモンズはその地域の生産共同体においてずっと管理されてきたし、それによってむしろ資源は保たれてきたのであり、むしろ現在の問題は管理コストの肥大化によるその消失や私有化にともなうコモンズの消失なのだ。つまり、彼のコモンズ放棄論を下支えしているはずのコモンズ観はかなり限定的だということになる。では彼の思考に限定を加えているものは何かといえば、それこそが「信」の問題に他ならない。すなわちみんなで共有するもの(コモンズ)への強烈な不信だ。これを当時の東西冷静という国際政治の文脈においてみると見えてくるものもありそうだがここでは示唆する程度にとどめておき、それがイデオロギーがもたらす作用であることを指摘しておこう。むしろより重要なのは、このことがコモンズに限られた問題ではないという点だ。現実社会の経済的把握も環境的危機の認識も、必ずしも誰にとっても明白な科学的事実であるとは限らないのだから、この「信」の在り方は現実社会の基本構造ともいえるだろう。たとえばナオミ・クラインが『これがすべてを変える』で詳らかにしているように、気候変動という事実すらも政治的立ち位置によっては相手側の持ち出す政策上の「トロイの木馬」にしか過ぎないのであり、そのとき、科学的な客観的事実(気候変動)と最新科学技術(気候変動への対処策)はどちらも「信」によって機能する(政党)政治の道具となり、そうなることでそもそもの事実や技術そのものとはかけ離れたものとして扱われることになってしまうのだ。
技術的解決への不信とは、すなわち科学と信念の完全な分離だ。「女主人」も、「声」も、そしてマルサスもハーディンも、この点においては同じ場所に立っている。そして後者の二人には政治的文脈があり、そこに与することはできない。一方的に貧困層や途上国の人口爆発を懸念する欺瞞は受け入れらないし、二項対立的に政治的に断じることもできない。ではわたしたちはどこに立つべきなのだろう。立つべき場をどう想像したら良いのだろう。だがこれは「エコ」ではありえない。「エコ」は極端に図式化すれば、技術的解決と経済的介入を盲信する市場原理主義イデオロギーの産物なのであり、その盲信は無責任と同義なのだ。それでは「生物(みんな)の未来」を守ることはできない。ここではこの「エコ」を裏返して、わたしたちの立つべき場を「コモンな(みんなの)オイコス」と呼び、想像し、考えたい。環境問題に対する具体的な解決策はまだない。だがそこに至るための筋道はここまでの議論で示せたと思う。それは「エコ」の基層に残滓的に流れ続けてきた「みんな(コモン)」への希求だ。不信の、悲観主義の裏には、逆説的だが、常にすでに失われたものとしての希望がある。それは当初オイコスが持っていた共同体のイメージなのではないだろうか。だがその内部の格差や差別はとりはらわれ、みんな(デモス)での統治(クラシー)とならなければならない。デモクラシーだ。ノスタルジックに過去の共同体を称揚して事足れりとするのではなく、それを求める残滓的な感情を認めながらそれをみんなのものにしていくのだ。「エコ」が湛える過去の残滓は、ここで「コモンな(みんなの)オイコス」を求める勃興的な感情となる。そのためにまず着手すべきは、個別的利害のアリーナとなってしまった政治をみんなのものにすることだろう。
〈引用文献〉
|
西 亮太(にし りょうた) 中央大学法学部准教授。専門はポストコロニアル批評。論文に「森崎和江のことば――運動論とエロスのゆくえ 1」、『詩と思想』第3巻374号(土曜美術社、2018年)118-124頁など。翻訳にヘザー・ブラウン「マルクスのジェンダーと家族論」『ニュクス』第3号(堀之内出版、2016年)54-65頁など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |