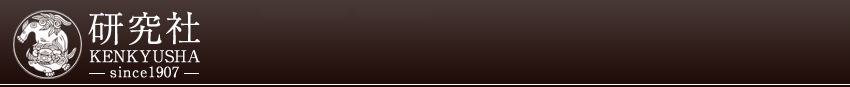

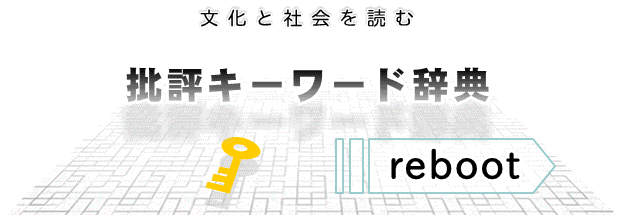
第3回
 | ありのままで |
「ありのままで」と聞くと、「ありのままの自分になるの」と歌う2013年のディズニー映画『アナと雪の女王』のテーマソングを思い出す人が多いだろう。すでに指摘されているように、“Let It Go” を「ありのままで」と訳すのは正確ではない。この映画を一言で説明するならば、触るものすべてを凍らせてしまう魔法の力を、父王に秘匿することを命じられた孤独のプリンセスのエルサが、自己の力を肯定し、妹アナと和解する物語だ。彼女の歌う“Let it go”の it とは、映画に即して考えると、彼女の父が述べた「力を隠せ。感情を抑制せよ。人に見せるな(Conceal it. Don't feel it. Don't let it show)」の it すなわち彼女の魔法の力である。つまり “Let it go” を説明的に理解するなら「自分の力が知られたって構わない」の意となる。ここで指摘したいのは、制約のある映画字幕の翻訳解釈の開陳ではなく、日本語の「ありのままで」がさまざまな意味を包括しうる言葉であることだ。
「ありのままで」という言葉は1990年代後半に流行していた。三作すべてが映画化された『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズ第一作の同名映画(小説 1996; 映画 2001)の見せ場で、コリン・ファース演じるマークがブリジットに告白する愛の言葉として、それは使われる。「君が好きだ。ありのままのキミが(Just as you are)」。あるがままのキミ。それは唯一無二のオンリー・ワン。英語では異なる二つの表現が、ともに「ありのままで」と訳されたのは、この言葉がそれだけ現代の日本語話者の心をつかむ言葉だからだろう。「ありのままで」は、現代を生きるあらゆる性の私たちにとっての隠れたキーワードだ。
都市で生きる独身女性の人生と恋愛を描いた同シリーズはまた、ポストフェミニズムを描いた作品としても知られる。ポストフェミニズムとは、論者によって定義が異なるが、メディア、フェミニズム批評、ポストモダン批評にいたるまで、文化・学術・政治の文脈において20世紀後半に台頭してきた現代のフェミニズムの状況を指す批評用語である。ポストフェミニズムの射程や可能性を見極める試みが2000年代以降とくにさかんだが、その定義についても標記についても論者によって異なる。直訳すれば「フェミニズムの後」を意味する、この語が示すのは、フェミニズムがかつて価値があったことは認めるが、普通選挙法をはじめ男女平等の目標は達成されたので、もはやそれは過去の遺物であり、女たちに必要なのはフェミニズムではなく、個人の努力で能力を磨くことだとする考え方である。
ポストフェミニズムという語はまた、新自由主義ときわめて親和的な用語でもある。シェリー・バジェオンによると、ポストフェミニズム言説においては、「平等が達成されたことを自明視することによって、女の達成に焦点」が置かれる。それゆえ「ライフ・スタイルや消費という選択を言祝ぐといったことに典型的に表されるような、個人としての自己定義および私人としての自己表現などのプロジェクトに着手することを、女たちに奨励する」(Budgeon 281)。言うなれば、ポストフェミニズムは、1960年後半から始まった第二波フェミニズムの主張を引き継ぐようなスタイルを見せながら、経済的主体としての自立の促進という看板を下ろさないという意味で、社会的な力に頼らず個人の能力によって経済的主体となることこそを唯一絶対の目標とする考え方と言ってよいだろう。
いわば、ポストフェミニズムの出現によって、フェミニストたちは問いを投げかけられた。フェミニズムは終わったのか、と。より正確に言うならば、第二波フェミニズムの意義は終わったのか、と。そうした問いに対して竹村和子は、フェミニズムはつねに過程の段階であり、もはや「女」という存在そのものに疑義があるのだから、その内実をつねに自己参照的に問いかけ続けようと提案する。フェミニズムとはつねに何かの後であり、生成過程にあるという竹村の提案を換言するならば、フェミニズムはつねにポストフェミニズムである。ポストフェミニズムを生きる私たちは、公共の支援なくしてキャリアと保育や家事をこなす――「すべてを持つ(have it all)」――ことを求められている。しかも、その要求は増えることはあっても減ることはなさそうだ。すべてを一人でやり繰りするなどという離れ業をできるのか。そんな不安を抱くのはブリジットだけではないだろう。
「ありのままで」という言葉には解放への希求が込められている。キミは最善を尽くしている。欠点があってもそのままでいいという肯定の言葉、もしくは、不安を緩和する言葉と言ってもよい。私たちはみな、仕事と生活の調和という課題を通して、フェミニズムへの距離はさまざまであれ、同じ難問に直面している。プライベートの時間など望むべくもなく、育児や家庭を持つことすら困難な現実があるにもかかわらず、ワークライフバランスを達成するべき目標として提示される。なんと息苦しいことか。「ありのままで」とは、そうした新自由主義的な目標から私たちを解放する言葉なのだ。
では、「ありのままで」という解放の言葉があれば、私たちはフェミニズムに万歳三唱ができるのか。かつてイギリスの作家 E・M・フォースタは、第二次大戦開戦の年に「民主主義に万歳二唱」と述べた。議会が私たちの代表たり得ているのか、そこでの議論が効率的なのかについては疑問が残るとしても、個人の重視と批評を許すという点において、民主主義は他の政治形態よりもマシである。万歳三唱は理想の社会――愛すべき共和国――にのみ値するものであって、民主主義はそれには値しない。万歳二唱で十分だ。これが彼の主張だ。彼の言う個人の重視とは多様性の尊重と言い換えてもよい。大戦という当時の文脈を踏まえないと分かり難いだろうが、彼にとっての万歳三唱が可能になる社会とは、信条や価値観を共有する人とともに生きる社会だ。同時に、同性愛が法的に禁じられていた当時のイギリスで、男性同性愛者の恋愛が成就する物語を描いた小説『モーリス』を死後出版したフォースタにとっての愛すべき共和国とは、同性愛が禁止されない社会でもある。そうした社会が実現した時、三唱目が可能になる。では、少なくともイギリスをはじめ世界各国で同性婚法が実現され、日本でも同性婚が条例化されつつある現在、フェミニズムに万歳三唱は値するのだろうか。この問いを「ありのままで」の深化を通じて考えてみよう。
 |
ポストフェミニズムの遮断幕と『アナ雪』の「ありのままで」 |
ありのままの自分。それを求める行為を日常語に置き換えるならば自分探し、もしくは、アイデンティティの追求と言ってよいだろう。アイデンティティという語は、新自由主義の産物だとマリー・モランは言う。現代においてこそポピュラーな表現であり、事実、概念としては古いアイデンティティという言葉が、今日用いられる意味で西洋社会に登場したのは20世紀転換期である。その用法は20世紀半ば以降一般に定着していく。それは第二波フェミニズムの台頭期であると同時に、新自由主義的思想が蔓延していく時代でもある。法的、個人的、社会的という三つのアイデンティティ概念の出現を説明して、モランは、これら三つの概念が互いに無関係な属性であるかのように語ることが可能だと理解されるようになり、そして、それらの概念のうち一つを選ばなければならないと思い込むような状態が新自由主義的思想から生まれている、と指摘する。新自由主義的文脈における自己探求――ありのままの自分探し――とは、一つだけを選ぶことなのである。
この現象とポストフェミニズム状況を接続してみよう。河野真太郎曰く、ポストフェミニズム状況においては、キャリアを追求するため戦う女と、家事や育児に追われて働き通しの女という二種類の人物の生産が多く見られる。ただし、彼女たちを勝ち組と負け組のように二項対立的に捉えるような見方こそがイデオロギー的な幻想だ。そうした対立構造の強調は女の労働と貧困を不可視にする。勝ち組を輝かせる光は、そうした女たちの状況を理解する遮断幕になっていると河野は言う。つまり、勝ち組とされる女たちは、個人が努力するという条件付きの実現不可能な夢である。その努力の前提が問われることはないままに、グローバルなエリート女性に皓々とスポットライトが当てられる。その光こそが遮断幕である。
そうした闇のような光の幕に包まれた私たちが、みんなの夢を希求するのは自然なことだろう。かつて『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』で、秦邦生は、ネットワーク――「みんな」の形成――への期待が高まる背景には、新自由主義的な個性化の理想化によってオンリー・ワンでありたいと願う気持ちがあり、それが集団との同一化を困難にさせる、と説明した。そして、音楽や文学作品を通して「みんな」が形成される可能性はあるが、そこに不自然な意図が感じられては成功しない。なぜなら、格差や社会的問題などについての思考が、家族、地域、階級などの個人を拘束する概念に向き合わせ、「みんな」という意識を持つことを躊躇させてしまうからだ(秦 135-36)。それは、オンリー・ワンであれば、集団の問題を共有しなくてよいというオンリー・ワンの呪縛だ。唯一無二に共通点はない、というわけだ。
そんな時に流行した『アナ雪』の「ありのままで」は、歌を通じて「みんな」を現実に形成してくれたかのようだ。映画館や YouTube を見ながら、みんなが「ありのままで」を歌う時、私たちはエルサの妹を大切に思いやる気持ちや、彼女の「フェミニスト的自由への衝動」(河野 29)に共感し歌ったのかもしれない。歌いながら無意識にせよ私たちは、人を思う気持ちが必ずしも異性愛の形を取らなくてもよいことに気付いたのかもしれない。その気持ちをシスターフッドと呼んでもよいだろうし、すでにインターネットで多くの人びとが指摘しているように、そこに女性同性愛志向の可能性を読んだ人もいるだろう。
だが、厳密な意味では、私たちの誰一人としてエルサの解放に共感することはできない。能力を抑制せよという命令は、父王が事故死してなおエルサを苦しめるほどに内面化された家父長制の呪いだ。その意味において彼女の苦悩はフェミニスト的な普遍性を持ち、また、その範囲において「ありのままで」は私たちにとっても解放の言葉となり得た。しかし、私たちとエルサには超えがたい溝がある。エルサがその力をありのままに揮う時、王位継承者の彼女は女王というオンリー・ワンになったのだ。エルサのような権力を持つ人などいるはずもないという意味では、彼女はグローバルなオンリー・ワンになったと言ってもよいだろう。エルサも私たちもオンリー・ワンの呪縛にとらわれているという意味で、「みんな」になり得ない。「ありのままで」という言葉は、解放の言語であるとともに、その事実を私たちから隠す遮断幕として機能しているのだ。
 |
万歳三唱の可能性を求めて――映画『美女と野獣』(2017) |
ポストフェミニズムの遮断幕を取り去るために私たちができることは何か。ポストフェミニズム時代に連続して映画化された『美女と野獣(Beauty and the Beasty)』のうち、とくに実写版から考えてみよう。物語は次の通りだ。ある晩、老女として現れた魔女が王子に一晩泊めてくれと願い出る。しかし、彼は、彼女の醜い外見ゆえに申し出を拒絶する。本当の姿を見ることができない王子に、老女/魔女は、彼が魔法の薔薇の花びらがすべて落ちる前に愛し愛されることを学ばなければ、彼も城の召使いたちも人間の姿に戻れないという呪いを掛ける。そうした呪いの城に偶然やって来た村娘ベルは、城の住人全員の希望となるが、彼女との結婚を望む自称村一番の美男子ガストンの策略によって、村人たちは野獣を殺そうと城を襲撃する。ガストンと王子との対決を通して、ベルと王子/野獣は互いの愛を確かめ、城の住人はみな人間の姿に戻る。これがアニメ版、実写版共通のあらすじだ。
実写版にはフェミニスト的要素がさらに強化される。村娘ベルが読書好きという点はアニメ版と同じだが、実写版のベルは女子教育に熱心なうえにエンジニアの才能も持ち合わせている。語り手もアニメ版のように男ではなく女である。しかし、本作のフェミニスト的主題がもっともよく現れるのは老女/魔女である。王子が重税によって国の美を独占して開宴される舞踏会に、老女を装って突如現れ、一晩の宿を願い出る彼女は、アニメ版には伝聞でしか登場しない。実写版の彼女は、老女・魔女・村のシングルマザーのアガットという三つのアイデンティティを持つ。彼女の一夜の避難場所の提供の願いは、承認ではなく再分配の要求だ。彼女は、城の住人には姿の変容、村の住人には記憶の抹消という二つの呪いを掛ける。つまり、彼女が要求したい相手は城と村の住人双方なのである。彼女は実写版にフェミニズムと新自由主義という文脈を与えている。
奇妙なことを言うようだが、自分の人生を切り拓こうとする能動的なフェミニストの登場人物を描いているものの、実写版は、ベルではなく王子/野獣の自分探しの物語として解釈するべきだろう。『アナ雪』が、エルサが女王になる物語であったように、『美女と野獣』は、野獣が王子(国の統治者)になる物語と言えば分かりやすいだろうか。事実、オープニングから最後の場面まで登場するのは王子/野獣であってベルではない。映画は、エマ・ワトソンを主演女優として宣伝するが、フェミニズム的解釈として最終的に残る事実は、長らく監禁状態にあった村娘が王子と上昇婚した。それだけだ。
王子/野獣の物語にはセクシュアリティと人種の多様性という現代的要素が加えられている。まず、ガストンの相棒ル・フウは明らかにガストンに恋心を抱く同性愛者だ。また数え切れないほどの白人・黒人・アジア系の美女が踊る冒頭の宴会場面で強調されるのは、変身前の王子が美の探求者であり、彼にとっての美の基準がグローバルであって人種は問わないことだ。
このように物語を位置づけると見えてくるのは、本作には、ベルと王子だけでなく、ガストンと野獣というもう一組の美男(Beauty)と野獣の存在だ(英語の Beauty は女とは限らない)。後者の二人はイヴ・K・セジウィックの指摘したホモソーシャルな関係で結ばれていると言ってもよいだろう。またガストンには戦争後遺症というアニメ版にはない要素が加わっている。彼が従事した戦争については「あの戦争以降、何かが欠落している気がしてならない」と本人が述べるように、本人すらもよく分からない。王子/野獣もガストンも何かが欠落した人物として描かれている。
ホモソーシャルな関係を読み込んでみると、本作が問題含みなフェミニスト・テキストであることに気付くだろう。第一に、アイシャドーや口紅などの化粧で入念に装う冒頭の王子/野獣を思い起こすならば、王子の装束とはいえ、彼はさながら服装倒錯者かドラァグ・クイーンだ。彼への忠告「怒り(temper)を抑えなさい」とは、そうした彼の気質(temper)の変更を要求している。冒頭の彼のジェンダー自認は男なのか女か。女たちに囲まれている彼の性的指向は異性愛なのか同性愛なのか。どちらも不明だ。明らかなのは、彼が最終的にベルとの異性愛婚を選んだことと、映画が彼のうなり声で幕を閉じることである。彼の気質はそのままだが、祝賀の宴で踊るベルはそのことに気付かない。
第二に、大団円での村と城の対立の解消は、すべての罪をガストンに負わせることで実現したが、しかし「野獣を殺せ」と叫び、城を襲撃したのは男女を含む村人全員であって、彼一人ではない。映画の冒頭で語られるように、城の住人は、村を含む世界とつながっていたらしいのだが、老女/魔女の呪いによって城外ではその存在を忘れ去られてしまう。より正確には、城外の人びとの記憶から完全に消される。城と村の関係は、あたかも冷戦時代の西側と東側のようだ。両者は互いを行き来できず遮断されている。いわば喪失したものが何かすら分からないメランコリー状態である。だから呪いが解け、姿は戻ったとしても、失ったものが何か分からないので、両者の記憶は戻りようがない。さらには従軍の後遺症によって苦しむガストン一人に隣人の殺害未遂という罪を負わせ、村人は自らが襲撃に加担した事実を忘れようとしている。ガストンのトラウマは城と村全体のものだ。村の住人と城の住人の再会は、記憶の回復ではなく、記憶の忘却の瞬間なのである。そうした忘却を抱えているのが城と村が一体化した社会だ。
第三に、ベルはたしかに女子教育というフェミニズムの課題に取り組もうとしているが、現実を十分に捉えていない。ベル役のエマ・ワトソンの出身国イギリスではすでに2000年代初頭に医学部進学は男子より女子が多く(Carvel)、さらに2016年には富裕層子弟が医学部進学者の多くを占めていることが議論の的となっている(Carrell)。映画のように女児の読み書き(初等教育)を中心に語ることは、フェミニズムの問題がここではないどこかの――たとえば発展途上国の――問題として見なすことだ。2018年の日本での医学部入試における女子受験者差別を指摘するまでもなく、女子教育は、進学を検討することすらできなかった人も含め、私たちみんなの問題だ。
男たちの欲望やセクシュアリティ。告発されない村人や城の住人の罪。アガットというシングルマザーの苦境への具体的解決の提示の欠落。不適切なフェミニズムの課題の提示。冒頭にいたはずのアジア系女性が大団円で消えてしまうこと。最終的には、セクシュアリティや人種の多様性がむしろ制限されていく。こうした読みを抑圧するのは何か。何が本作品でのポストフェミニズムの遮断幕なのか。その仕掛けの一つがエマ・ワトソンというスターだろう。ハリー・ポッター・シリーズで一躍若手人気女優となった彼女の存在によって、私たちは実写版『美女と野獣』を女の物語として読むことを求められているのだ。
最初の問いに戻ろう。同性婚が達成されれば、フェミニズムに万歳三唱できるのか。否。それだけでは不十分だ。万歳三唱を実現するために、私たちがすべきことはたくさんある。王子でも野獣でも誰でもが自らのジェンダーやセクシュアリティについて話したいと思う時、安心して話すことができる社会を作ること。ガストンをテロリストとして社会から排除するのではなく、彼のような戦争神経症をもたらさない社会を作ること。社会保障を受けられず再分配を望むアガットを魔女として棄却するのではなく、シングル女性の困窮を社会全体の問題として取り組むこと。私たちみんなの問題を語ることを中断させるものが何かと問うこと。ありのままでいてもよい。しかし、ありのままでいられない人を思いいたすこと。それらすべてがフェミニズムの課題である。ありのままでいることを問い直そう。そして、私たちはフェミニズムに万歳三唱するかどうかについて、議論を始めることができるだろう。
〈参考文献〉
|
松永 典子(まつなが のりこ) 早稲田大学教育学部准教授。専門は 20 世紀から現代までのイギリス文学・文化およびジェンダー理論などの批評理論。共編著に『終わらないフェミニズム――「働く」女たちの言葉と欲望』 (日本ヴァージニア・ウルフ協会・河野真太郎・麻生えりか・秦邦生・松永典子編著)(研究社、2016年)、共訳書に『マクミラン版世界女性人名大辞典』(竹村和子訳監修)(国書刊行会、2005年)など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |