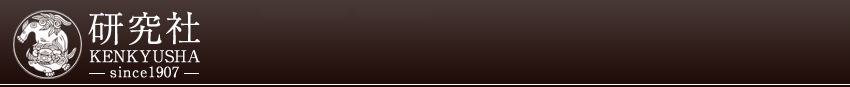

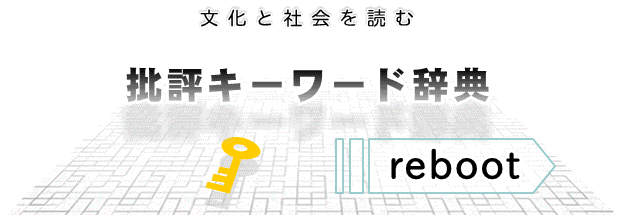
第11回 [最終回]
 | 科学 |
現在、専門家と専門知はこれまでになく軽視されているように見える。
本稿を書いている2020年3月現在、世界は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに見舞われている。新型ウイルスであるがゆえにワクチンや特効薬はまだ存在せず、また致死率や感染力・感染方法など、正確には分かっていないために、情報が錯綜し、ウイルス感染への対応策も国によって千差万別となっている。
確かに、このウイルス感染症への対策が混乱を極めているのは情報不足が原因ではある。だが、たとえそうであっても、日本政府の対応に関してのある疑念がぬぐえない。それが冒頭に述べた、専門家/専門知識の軽視だ。
2月27日木曜日に、安倍晋三首相は、全国の小中高校の休校を「要請」した。予告のない、かなり突然の要請に大きな動揺と混乱が広がる中、次の週には、最終学年の卒業式も終わっていない全国の小中高校は軒並み休校となり、3月中は学校が再開される見込みはどうやら薄い。全国の美術館や図書館などは休館し、コンサートや演劇、講演会といった人の多く集まるイベントは相次いで中止となった。
このような措置が、それを取らなかった場合と比べて、感染の拡大をどの程度抑えたかを判断することは筆者にはできない。ただ気になるのは、2月28日に行われた国会(衆議院予算委員会)答弁で、安倍首相が、学校の休校要請については「専門家の意見をうかがったものではない」と述べたことである。あくまで安倍首相個人の政治的判断として要請を行ったというのだ。
繰り返すが、ここでは休校による感染抑制の効果を判断・評価したいわけではないし、それはできない。そうではなく、このような重大な政治的判断について、「専門家の意見を聞いていない」と首相が答弁できてしまうのはどういうわけなのか、それを問題にしたいのである。
おそらくこれは、新型コロナウイルス感染症に限った問題ではないし、また安倍首相だけの問題でもない。政治的判断だけではなく、さまざまな判断に専門知識は必要ないという文化が、長い時間をかけて醸成されてきた結果のひとつの現れが、現在のパンデミックに対する政府の対応なのではないか。
このことは、2011年、つまり東日本大震災とそれによって引き起こされた福島第一原子力発電所におけるメルトダウン、そして放射性物質の拡散という経験を私たちが経たことを考えると、首をひねるしかない。私たちはあの時、絶望的に錯綜する情報の中で、専門家の科学的知識を藁のごとくつかみ、なんとか専門知にもとづいた判断をしようと努力しなかったか。それともそれは筆者だけに見えていた世界であって、実際には大半の人びとは専門家の知識なぞ頼りにはしなかったのだろうか。もしくは、その後の展開の中で専門家に対する根本的な幻滅を覚えたのか(そういえばそのような幻滅を、覚えた瞬間が私にも確かにあった)。
今回のキーワードは「科学」である。だが、まっすぐにこのキーワードに向かうのではなく、この専門家/専門知の不信という問題からアプローチしていきたい。
 |
専門家への嫌悪 |
専門家/専門知識不信は、かなり広く根深い現象である。日本からもう少し例を取るなら、近年の大学入試改革にもそれは見て取れる。現在政府は、「高大接続改革」という大きな枠組みの下で、大学入試を改革しようとしている。具体的にはこれまでの大学入試センター試験を改め、大学入学共通試験をスタートさせようとしている。そのうち英語については、「四技能」(つまり、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング)の旗印の下に、さまざまな業者による英語試験を入学試験の一部に取りこむ、そして将来的には完全に置きかえることが計画された。だが、この計画が策定されるにあたって、英語教育や英語のテストによる能力測定の専門家が、決定に影響力を持ちうる形で関わった形跡はない。
例えば、テストに関して基本的で重要な視点は、ある能力を直接に測ることが、その能力を上昇させることにつながるとは限らない、ということである。英語試験に関して言い換えれば、例えばスピーキングの試験を行うことが、スピーキング能力を高めるとは限らない。阿部公彦が主張するように、現状のままスピーキングを試験に入れることによって、単に英語力全体が低下する可能性が高いのである。
だが、実際の改革において、そのような専門家の意見は顧みられることはなく、むしろ試験を実施する私企業の顔色を見る形で、民間試験導入へとなだれ込んでいった。ただし、当面今年度に関しては、(やはり専門家たちが指摘してきたはずの)技術的な問題が解決されず、民間試験導入は見送られた。
これは一例である。だが、この一例は、日本の文教政策が科学的な発想を欠いていること、つまり現象を観察し、それを分析・評価し、それにもとづいて政策を決定するという基本的な手続きを欠いていることを示唆している。これについては、佐藤郁哉が『大学改革の迷走』で、偽りの PDCA プロセスや「エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング(エビデンスにもとづいた政策決定)」が、実際は「ポリシー・ベースト・エビデンス・メイキング(政策を前提としてのエビデンスの捏造)」になっていることを指摘している。
さらに視野を広げるなら、このような専門家軽視の傾向は、日本だけではなくアメリカにも蔓延している。というより、専門家軽視のより広い心性として反知性主義は、アメリカの文化の重要な一部分である。そのことを赤裸々に描いてみせたのはトム・ニコルズ(『専門知は、もういらないのか』)である。ニコルズによる、アメリカでのさまざまな反知性主義と専門家嫌悪の現象の列挙を締めくくるのはもちろんドナルド・トランプだ。彼は核戦略をはじめとする重要な政治的課題についての驚くべき無知をさらけ出しながら選挙戦を戦ったにもかかわらず、アメリカ大統領となった。いや、むしろ、無知をさらけ出したがゆえに大統領になれたと言った方が正確だろう。ニコルズ曰く、「国の指導者が目に見える知性を有していたらそれ自体が信用ならない性質だと思い込んでいる人々は、トランプに自分たちのために戦う闘士を見た」のである。
ニコルズによれば、このようなトランプ人気の土壌を共有するのが、例えば地球温暖化否定派やワクチン否定派の反知性主義である。そういった言説とその支持者にとっては、なんらかの積極的な真実を知っているというよりは、専門家の意見(地球温暖化、ワクチンの効能と必要)が一定の立場と利害から発せられたフェイクであることを「見抜いた」と思いこむことの方が重要なのである。
 |
反知性主義の系譜? |
ニコルズの説明は、日本の私たちにとっても身に覚えのあるものだろう。ただし、ニコルズの本が私たちの状況の解決に向けた特効薬になってくれるかどうかと言えば、それは残念ながらなさそうである。反知性主義に対するニコルズの嘆き節が熱を帯びれば帯びるほど、そのようなレトリックを権威主義的だと感じる「反知性主義者」の反応は、さらに過激化していくことが予想されるのだ。現在の反知性主義には、そのような落とし穴がある。反知性主義は、まさにそれ自身への批判からそのエネルギーを得てしまうのだ。
では、なすべきことは何だろうか。ひとつには、専門知軽視と反知性主義を歴史化することかもしれない。ミチコ・カクタニの『真実の終わり』をそのような試みとして読むことは可能だろうか。カクタニは、現在の反知性主義の源流を、主にフランス思想に由来するポストモダニズムと、それを受容した1960年代以降アメリカの新左翼に見る。もちろん新左翼による「文化戦争」やポストモダニズムがそのままトランプに流れこむわけではない。そこでは「乗っ取り」があった。カクタニの記述は以下のようなものである。
相対主義の影響力は一九六〇年代に文化戦争の幕が開いて以降、高まりつつあった。当時それは、西洋中心的、ブルジョア的、男性支配的な思想のバイアスを暴くことに熱心な新左翼と、普遍的な真実を否定するポストモダニズムの真理を唱える学者に採用された。あるのは小さな個人的な真実、つまりその時々の文化的・社会的背景によって形成された認識に過ぎないというのだ。その後、相対主義的な主張は右派のポピュリストに乗っ取られた。進化論を否定する創造論者や気候変動否定論者は、自らの考えを科学的根拠のある理論と並べて教えるよう要求している。
カクタニが頼るのは、新左翼とポストモダニズムの歴史というよりは、その通俗化された歴史でしかない。つまり、客観的な現実の存在を否定するポストモダニズムは1960年代以降の文化戦争そして(この言葉は使われないが)アイデンティティ主義に利用され、それが(「乗っ取り」を介して)まっすぐに右派ポピュリズムにつながっているという「歴史」である。このような「歴史」は、それが何かを明らかにする以上に隠ぺいしてしまう。それが隠ぺいするのは、文化戦争が持っていたある種の必要性=必然性であり、ポストモダニズムがもたらした、もしくはもたらし得たかもしれなかった解放作用だ。また、「乗っ取り」がいかなる歴史・社会的作用によって起こったのか、それが説明されないかぎり、このような「歴史化」には意味はないだろう。
カクタニは、ポストモダニズムの主張を、デリダやド・マンといった思想家のテクストに依拠することなく曲解するような俗流の解釈を、それが俗流であるということは理解しながらも反論はせずに受け容れている。彼らが客観的な事実・現実が存在しないと実定的な意味で主張したことは一度もない。そうではなく、脱構築は「客観的な事実」がさまざまな力の作用によって構築されていることを主張したのである。この二つの違いは理解していただけるだろうか。脱構築は、誤解を恐れずに言えば、「現実」の存在については前提としている。だが、人間がその現実を認識し、言語化するにあたって、現実が透明に認識に届き、言語に体現されることはあり得ない。そこにはさまざまな力が介在するのだ。そして、ついでに言うならば、その「さまざまな力」も厳然とした客観的存在である。そのような力のありようを問題にするのが脱構築なのだ。
カクタニは、違う表現を使うと、ポストモダニズム的相対主義かリアリズム的客観主義か(後者の表現は本人は使わないが)、というおなじみの二項対立を設定することで、前者を批判する。だが、その過程で、ポストモダニズムが備えていた、「権力の働きをめぐるリアリズム」を見失ったのである。そしてその結果、トランプ主義=ポスト・トゥルース主義に対する肝心の批判力を失った。[注]
 |
「科学」の原風景へ |
ニコルズやカクタニの陥った道を避けるにはどうすればよいのだろうか。ここでようやく、本稿がかかげるキーワード、「科学」の出番となる。反知性主義や専門家/専門知軽視という現象は、より広く「科学」というキーワードの系譜を考えることで解きほぐすことができるかもしれない。(前もって断っておくと、本連載の出発点となる『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』では、「技術」そして「信じる」において、この問題は別の形で検討された。今回は、それとはまた別の文脈において、ただし普遍的な関連性を持った鍵語として「科学」を検討したい。) そして、やはり依拠すべきなのは、本連載の基盤に存在しつづけた、レイモンド・ウィリアムズの『キーワード辞典』だ。
『キーワード辞典』の「科学 science」の項目は熟読に値する。そこでウィリアムズは、science がフランス語の science、ラテン語の scientia――つまり「知」を意味する言葉――を前形として14世紀に英語に入ってきたことを確認する。そしてしばらくの間は、科学(science)は技芸(art)と交換可能な形で使われたという(478-79頁)。
しかし17世紀半ばから、「科学」と「技芸」は分裂を始め、それらの言葉は「理論的な知識を必要とする技術と、習熟しさえすればいい技術との区別」(479頁)を表現するようになった。
ウィリアムズの洞察が輝きを放つのは、この後、18世紀以降の「科学」の歴史における「経験 experience」と「実験 experiment」との区別の重要性を論じる段においてである。同じ『キーワード辞典』から関連語 empirical(経験的)の項目を見ると、これらの語は18世紀末まではじつは交換可能であったことが確認されている(187頁)。言われてみればその通りで、経験であれ実験であれ、なんらか過去に経験されたデータの集積のこと、という広い意味では同じものなのである。だが、これらの語が分離するにしたがって、「科学」の意味も限定を加えられていくことになる。この間の事情を、ウィリアムズの言葉を引用して確認しておこう。
「経験」は、実際的、習慣的な知識と、外的な(「客観的」な)知識とは異なる内的な(「主観的」な)知識という二つの方向に限定できるだろう。これらの語義はそれぞれすでに「経験」という語に含まれていたものだが、「実験」(あらかじめ準備を整えたうえで、ある事象を秩序だって観察すること)と区別することによって、「経験」にも意味を特定するための新たな重点が加わった。自然観が変わったため、方法や論証はとくに「外的世界」に対して行われるものだという考え方が促進され、こうして「自然」の理論的、系統的な研究をさす science の意味が生まれてくる条件がすっかり整った。とすれば、別の種類の「経験」(ひとつは形而上学的・宗教的領域、次は社会的・政治的領域、もうひとつは、とくに芸術と新しく結びつけられて考えられはじめていた「感情」や「精神生活」の領域)に適用される理論や方法は、science ではない何か別のものとして区別されることになるのだろう。(480-81頁)
私たちが14世紀以来の長い歴史の果てに、いかなる「科学」の意味を受け取ったのか――ウィリアムズの記述はそのような問題設定でものを見る視点を与えてくれる。かつては科学とは〈経験 experience=実験 experiment〉の下に得られた〈知 science=技芸 art〉であった。それが、現代的な意味での客観的「実験」にもとづく「(自然)科学」となったとき、(これまた現代的な意味での、主観性と結びつけられた)「経験」にもとづく技芸=芸術 art(art という言葉の中に起きた分裂も重要だがここでは割愛する)は、その外側へと放逐されたのである。
前段までで検討した、極端な形ではトランプに結実した「反知性主義」または「専門家ぎらい」とは、時代を短いスパンで見れば新自由主義以降に隆盛してきた右派ポピュリズムのメンタリティとして(もしくはカクタニが主張するように、それと軌を一にするポストモダニズムのメンタリティとして)説明できるのかもしれないが、時間軸をより長く取れば、「科学」の意味が限定されていった数世紀の歴史の中で、「科学」から放逐されてしまった意味の回帰として見ることができる。つまり、反知性主義は、〈経験=実験〉から放逐されてしまった「経験」のあるひとつの(それが全てではない)形での回帰ではないか。トランプ主義を支える欲望のありかは、そこにあるのではないか。おそらく、トランプ主義的な専門家への懐疑には、「専門家」という言葉についての複雑な転回がある。ウィリアムズが述べたような系譜においては、専門家とは経験と実験が分離され、科学が実験にもとづくものとなっていった時代において、そういった実験/科学の知を独占する存在である。だが、トランプ主義的反知性主義では、そのような専門家は実践的な「知」を持ち得ていない存在となる。平たく言えば、「世間知らず」な存在となる。その考え方においては真の知――「世間知」――を持っているのは現場での「経験」を持つ「ふつう」の人びとだ、ということになる。
だが、そのような事情を理解した上で、私たちがさらに理解せねばならないのは、そのような「経験」はそれ自体分断され、部分化してしまった経験であるということだ。反知性主義者の「経験」は、それ自体、全体的な「科学=知 science」から疎外されている。かといって、取り急ぎつけ加えるなら、その全体的「科学=知」はどの一人の専門家の専有物でもあり得ない。近代の私たちはみな科学=知から疎外されている。ニコルズもカクタニも、避けようもなくそのような疎外の中でものを書いている。
 |
ソーカル事件を思い出す |
その疎外状況は、カクタニ自身が設定している二項対立とは何か別のものへと読み替えられる必要がある。カクタニは、自らの議論を十分に歴史化し得ておらず、ポストモダニズム的相対主義/リアリズム的客観主義の二項対立の歴史性を意識化し得ていないのだが、それを歴史化する足がかりとして、カクタニが彼女の選んだ主題を論じるなら当然に触れてしかるべきだったある事件を「思い出す」ことが役に立つかもしれない。それは、「ソーカル事件」である。
ソーカル事件とは、1995年にニューヨーク大学物理学教授であるアラン・ソーカルが学術誌『ソーシャル・テクスト』に、ポストモダン思想風のレトリックと、嘘だらけの物理学の知識を詰め込んだ疑似論文を投稿し、それが掲載されてしまったという事件である。ソーカルはポストモダン思想の一部が自然科学の知を、いい加減なレトリックの水準だけで利用していることを告発するためにそのような捏造を行ったのだが、彼の政治的意図は、単なる文系・理系の対立にとどまるものではなかった。ソーカル自身の、自分は「隠れもしない旧来の左翼であり、脱構築がいかにして労働者階級を助けることになるのか皆目見当もつかなかった」という述懐は非常に示唆的である(Sokal and Bricmont 269)。ソーカルもここで、カクタニが述べたような二項対立の中で語っている。つまり、ポストモダニズム的相対主義とリアリズム的客観主義である。ソーカルの場合、後者の立場は、上記の一節から敷衍するなら、「労働者階級を助ける具体的な方法を知っている旧左翼」の立場である。
ソーカル事件の場合、人文学(的なもの)と自然科学(的なもの)の対立が、カクタニ的なポストモダニズムとリアリズムとの対立に重ね合わされている。前節の最後に述べたことからすると、ここには奇妙なひねりが存在する。ソーカルに言わせれば、自分(たち)こそが労働者階級を助ける方法、つまりこう言ってよければ世間知を持つ者である。ポストモダン思想に代表される人文学は、そういったものから遊離した知である、というわけだ。私たちはこのような態度にこそ、トランプ主義的な反知性主義(もしくは「経験」主義)の萌芽を見いだせないだろうか。だとすればカクタニは、そのようなソーカルの態度を我知らず反復している。その態度を反復するということは、彼女自身が批判するトランプ主義を深い水準で反復しているということだ。
ところで、ソーカル事件は歴史上、何度も反復されてきた。これについては拙著(『〈田舎と都会〉の系譜学』)の第8章で論じた。一度目は19世紀、小説家オルダス・ハクスリーの祖父で進化論学者のトマス・ヘンリー・ハクスリーと、文化批評家マシュー・アーノルドとの間で戦わされた論争、そして20世紀も後半に入って、物理学者で小説家の C. P. スノウの「二つの文化」講演に対する、文芸批評家 F. R. リーヴィスの激烈な批判である。
残念ながらこれらの論争の細部を紹介することは紙幅が許さない。だが、ここで確認しておきたいのは、これら三つの論争は、一見「文系対理系」または「人文学対自然科学」の対立のように見えるかもしれないが、じつは本質はそこにはなく、これらの論争は、ウィリアムズが「科学」という言葉の系譜の根源に見いだしたような全体的な知としての科学を、そして知の涵養としての教育をめぐるものだったということが重要である。例えばハクスリーが教育における科学の重要性を訴えたのに対して、アーノルドは古典語を中心とする言語の重要性を主張した、というように。そして、私がここでこれらの論争に遡行しているのは、ほかならぬウィリアムズが、ハクスリーを高く評価しており、彼の伝記の書評の中で次のような示唆的な洞察を述べているためだ。
科学と文化との関係は、なんといっても、その両者の不適切な定義によって混乱したものになってきた。それらの分離は、全体的な社会的圧力のもとでの、おおきな知的歪曲のしるしである。それは歴史的には、いっぽうではロマン派、他方では機械論的唯物論者によるものだ。(“Science and Culture” 584)
ここでロマン派と呼ばれているのはアーノルドのことであると考えて大過ないだろう。アーノルドから上記の F. R. リーヴィスにいたる、少数者の「文化」が社会全体の秩序を守るという理念の系譜である。
では「機械論的唯物論者」がハクスリーのことなのかといえば、そうではない。上記の通り、ウィリアムズはハクスリーを評価するのだが、それは彼がまさにロマン派/機械論的唯物論者の対立そのものを超えていくからである。むしろ、「機械論的唯物論」とは、ここまで見てきた中では、カクタニ=ソーカルが称揚するリアリズム的客観主義のことである。
この対立は、まさにここまで問題にしてきた対立そのものだ。つまり、人文系と理系の対立であり、経験と実験の対立であり、非科学と科学の対立だ。それは、社会の全体性をつかさどるはずの知の分断の系譜と言っていいだろう。
ただし、この系譜には転回が存在し、ウィリアムズの言うロマン派的な立場はいまやすっかり人文学には不可能になってしまった(その意味で、ソーカルの人文学批判はすでに時代遅れだった)。その代わりに、現代のロマン派と言えるのは、例えば AI(人工知能)について、シンギュラリティ(AI が人間の頭脳の処理能力を超えるとされる時点)が訪れることで人間社会が根本的で全面的な変容をこうむるだろうという予測を喧伝する人びとである。彼らは、技術決定論者のように見えるかもしれない。しかし、その論理において彼らは、「少数者の文化」が社会の全体の秩序を保守していくのだと夢想した、アーノルド的文化論者の系譜にある。
だが、私たちは、彼らの願望、欲望の水準を見すえるべきだ。つまり、AI という知、もしくは AI についての知が社会をめぐる全体的な知である(ありたい)という欲望である。それを見落として、シンギュラリティをめぐる言説が単なる「科学的」虚偽であるとして事足りると考えるのは、機械論的唯物論=リアリズム的客観主義の落とし穴にはまることになる。
私たち自身も含め本論の登場人物たち(ニコルズ、カクタニ、トランプ……)はみなここまで述べたような分断にとらわれた存在であった。それに対し、ウィリアムズのハクスリー評価の正当性をここで評価するのは不可能であるものの、少なくともウィリアムズにとってハクスリーはこういった分断を超えうる思想家であった。現代において、ハクスリーの道を構想することは可能だろうか?
 |
共通文化としての科学 |
私たちが目指すべきなのは、反知性主義の欲望と、反-反知性主義の欲望の双方を、分断を超えた全体的な「科学=知」へと向けた欲望に読み替え、向け直すことだ。そもそも、アメリカ流であれなんであれ、反知性主義は民主主義への欲望でもある。その観点からすると、反知性主義にはすでに全体的な知への欲望が胚胎しているはずなのである。ここにいたって、この全体的な「科学=知」は、レイモンド・ウィリアムズの言う「共通文化」に似た何かに近づいていく。ウィリアムズにとって共通文化とは、なんらか形をなした、与えられた実体ではない。それはあるプロセスの名前である。ウィリアムズが次のように共通文化を定義するとき、それは同時に科学の定義にもなりうるだろう。
ある現存する経験の一部がある具体的な方法で分節化され、たんにほかの人びとへと拡大され――そして教えられ――、その結果ほかの人びとが共有物として所有するようなことがあれば、それは共通文化(コモン・カルチャー)とはならない(共有された文化(カルチャー・イン・コモン)と呼ぶことは可能であるにしても)。というのも、最初に強調したこの必然的帰結とは、ある人民の文化とはすべての構成員がその生活の活動において創造にあずかるようなものでしかありえないということであり、共通文化とは少数派が考え信じることを全般的に拡張したものではなく、人民全体が意味や価値の創造と表明に参加し、またそれにつづいてある意味を選びとり、ある価値を選びとる行為に参加できるような状況の創造にほかならないからだ。(71頁)
私たちの疎外状況、つまりポストモダニズム的相対主義とリアリズム的客観主義という形で最近では体現された、「科学」の分断の状況は、それ自体言ってみればウィリアムズの言う「共有された文化(カルチャー・イン・コモン)」である。私たちはそれを超克していかなければならない。私が本稿で「権力の働きをめぐるリアリズム」と呼んだポストモダニズムの最良の部分は、まさにそのような超克を目指したものだった。それは「相対主義か客観主義か」という形で「コモン」なものになってしまった科学とそれをめぐる分断をもう一度解体し、別の「コモン」なものへと動かしていくプロセス、つまり共通文化としての科学のプロセスを発動させるものなのだ。確かに、共通文化を口にするウィリアムズが指ししめすのははるか遠くである。だが、科学の疎外に気づいた私たちは、そのはるかな道のりに向けた歩みを、自分たちがすでに踏み出していたことに気づくはずである。
〈参照文献〉
|
河野 真太郎(こうの しんたろう) 専修大学法学部教授。専門はイギリスの文化と社会、新自由主義と文化。著書に『戦う姫、働く少女』(堀之内出版、2017年)など。共編著に『愛と戦いのイギリス文化史――1951-2010年』(慶応義塾大学出版会、2011年)など。訳書にレイモンド・ウィリアムズ『共通文化にむけて――文化研究I』(共訳、みすず書房、2013年)『想像力の時制――文化研究II』(共訳、みすず書房、2016年)など。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |