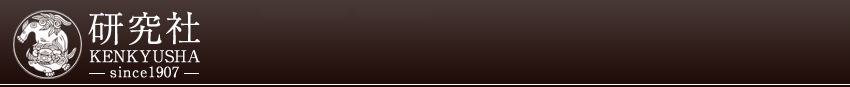


|
これまで20回にわたり連載を続けて参りました「〈役割語〉トークライブ!」も、今回をもって最終回となりました。今回は、これまでの内容を振り返りながら、改めて「キャラクター」と「役割語」の関係について、考えてみたいと思います。
 |
キャラクターと「同一性」「固有性」 |
今回、参考にしたいのは斎藤(2011)『キャラクター精神分析――マンガ・文学・日本人』です。この本の中で、斎藤環氏は「キャラクターの定義。それは「同一性を伝達するもの」である。逆の言い方も成り立つ。同一性を伝達する存在は、すべてキャラクターである、とも。」と述べています。さらに「ある存在が、時空を超えて同一であると認識されるためには、それが「人間」であるか、もしくは人間に関連づけられた物でなければならない」とし、次のように説明されています。
これは僕たちの現実認識において、人間にのみ強い固有性が与えられているからだ。哲学的な問題としては、もちろん車に限らず事物の固有性を取り扱うことは可能だ。しかし僕たちの日常においては、事物の固有性は、それが人間に関連づけられない限り、ほとんど問題にならない。言い換えるなら、個人の固有性と個人の同一性とはしばしば同義であると同時に、それは実質的には、ほぼ人間が占有する属性なのである。 (斎藤 2011:pp. 235〜246)
斎藤氏の議論は、フロイト、ラカンに連なる精神分析理論に基づくものであり、その用語体系と本稿の議論を厳密にすりあわせていくことは骨の折れる作業なので、今はそこには立ち入らず、氏の「同一性」「固有性」という用語をヒントに、私たちの考えを進めていきたいと思います(以後、「固有性」は私の用語で「個体性」あるいは「唯一性」と読み替えることにします)。しかしながら、「僕たちの現実認識において、人間にのみ強い固有性が与えられている」「個人の固有性と個人の同一性とはしばしば同義であると同時に、それは実質的には、ほぼ人間が占有する属性」という認識は、私たちにとっても大きな議論の拠り所となるでしょう。また、斎藤氏は人間の特徴として「固有性」があり、個々の人間を超えて共有される「同一性」を表現するものを「キャラ」として区別していますが、この区別についても意識していきたいと思います。
 |
定延(2011)の「キャラクタ」理論再訪 |
ここで、この「〈役割語〉トークライブ!」第3回でも採り上げた、定延(2011)の「キャラクタ理論」を振り返ってみたいと思います。定延氏は、さまざまな言語現象を考える際に、従来のメジャーな言語理論で前提とされていた「ある人格がスタイルを切り替える」という「人格―スタイル」の二段階説に異を唱え、「人格―キャラクタ―スタイル」の三段階説を新たに唱えられました(定延氏は、一般の文脈で用いられる「キャラクター」と区別し、氏の独自の言語理論の用語であることを強調するために、敢えて「キャラクタ」と、延ばさない表記を用いていますが、私の議論の中では、定延理論の引用部分を除き、一般の用語に合わせて「キャラクター」という表記を用いることとします)。
ここで、“人格” は、普通はまず変わらないもの、“スタイル” は変えても差し支えないし、むしろ場面に応じて変えるべきもの(例えば丁寧体と普通体[=ため口])だが、人物像の中でも “キャラクタ” は、意識して変えることは可能なのだが、それを変えるところを人に見られてしまうと「(キャラクタの変化が)何事であるかすぐに察しがついてしまうが、見られた方も見た方も気まずいもの」(p. 14)としています。図示すると、こうです。
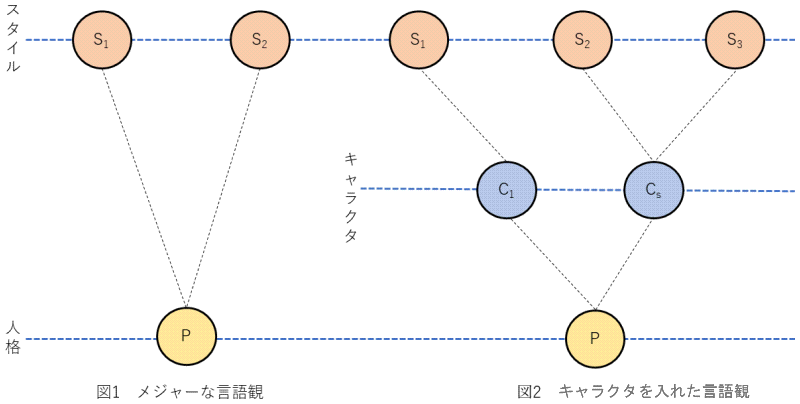
ここで、「キャラクタ」の同一性と変化について語られている点が興味深いです。
また、現実にこの社会で生きている私たちは、複数のコミュニティに所属しているのが普通で、コミュニティごとに違う “顔”=キャラクターで他者と接しているのが普通です。このことも、「〈役割語〉トークライブ!」第2回で、「大学の女性教員 “A子さん”」を例に取って示しました。つまり、キャラクターとは、コミュニティの中で接している人々に向けた “ペルソナ”(=仮面)であり、私たちはしょっちゅうこの仮面を付け替えているのですが、人前で公然と仮面を掛け替えるのははばかられる、ということでしょう。そして、仮面の奥にある一人の個人が「人格」と呼んでいる存在である、ということになります。
 |
“幻想” としての「キャラクター」 |
定延氏はここでは言語の話をしているので、一番表層にある「スタイル」は、いわゆるスピーチ・スタイルであり、言語的なさまざまな記号(語彙、語法、固有の言い回し、音声的特徴等)の組み合わせに当たります。一方で定延氏は「表現キャラクタ」という概念も立てており、これは言語以外の仕草、表情、行動等の表現を指し示しています(例「ニタリとほくそ笑む」)。また、もっと視覚的な服装、ヘアスタイル、アクセサリ等の組み合わせ等も大いにキャラクターを表現することでしょう。つまりこれらは、実際に観察可能な「属性」の集合です。これに対し、キャラクターそのものを実体として指し示すことは、実はできません。
例えば次の図3 のようなイラストをもって、キャラクターの表現であると言うことができるかというと、それも当たりません。
図3 いろいろな人物像のイラスト
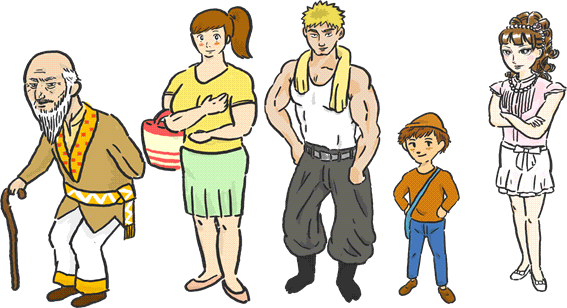
つまりこれらのイラストも、キャラクターの外見を線や色彩の組み合わせという属性によってキャラクターを想起させているだけで、これらも一種の視覚的「スタイル」に他ならないのです。ですから、イラストの人物と役割語(例「ワシが知っておるんじゃ」「ぼくが知ってるのさ」等)を結び付ける「役割語クイズ」(「〈役割語〉トークライブ!」第1回)は、キャラクターとスピーチ・スタイルを結び付けるというより、厳密には、同一キャラクターにつながる言語的属性と視覚的属性を結び付けるという作業であったということになります。
つまりは、キャラクターとは、さまざまな言語的・視覚的その他の属性のまとまりによって浮かび上がる “幻想” あるいは “虚構” に過ぎないと言えるのではないでしょうか。そこにある種の “まとまり” あるいは “同一性” を感じさせるのは、その背後に確固たる “人格” が存在する、と私たちが仮定しているから、ということにもなります。
 |
フィクションと「人格」 |
キャラクターが属性の集合であり、変化可能であるが普通は人前で変えるところを見せないものだとすると、そのキャラクター変化の前後において「同一性」を担保する「人格」とはどのようなものでしょうか。それは、キャラクターの “虚構性” に対する “実存” と言えるのでしょうか。
現実世界に即して言えば、例えば次のように言えるかもしれません。すなわち、「誕生からその死までの連続する時間内で、同一時間において同一空間を占有する唯一の個体」と。さらに、生物学的・言語学的な法則により、両親等の親族がそれぞれ唯一に決まり、誕生地が決まり、母語が決定され、また生物学的な性も決定されます。もっと言えば、現代科学における究極の生物学的な同一性・個体性とは「DNA」かもしれません(韓流ドラマを見ていると、さかんに DNA 鑑定が出てくることに驚かされます)。
また、社会的には、誕生地や両親の決定によって国籍が決まります。遺産相続や子供、親の養育義務なども生じます。これらの属性は属性の中でも、最も根源的に「人格」にまつわる属性と言ってよいでしょう。
ただしこれらの属性は人間であるからこそ決まるものであり、植物とか菌類とか人造物とかに範囲を広げると、たちまちその個体性が揺らぎ始めます。また動物であっても、ペットや家畜など人間に身近な対象でない限り、個体を識別することはなかなか困難であることが一般的です。このような意味で、人間以外に「個体」の概念を適用するのは、多かれ少なかれ「擬人化」の要素があるということが理解できます。
このように、少なくとも人間でありさえすれば、かなり揺るぎない拠り所となるはずの “人格”=「個体性」ですが、しかし現実世界でも、「個体性」をめぐる事件がニュースを賑わせています。例えば、「私の親は誰なのか」「この死体は誰だったのか」「この事件の犯人は誰なのか」等々。さらに、フィクションともなると、個体の揺らぎを扱った仕掛けがたくさん登場します。例えば「憑依」「二重(多重)人格」「記憶喪失」「洗脳」「サイボーグ化」「ドッペルゲンガー/生き霊」「幽霊/霊魂」「生まれ変わり/転生」「多重世界」等々。霊や魂のことを考え始めると、実は宗教というものはさまざまな個体性・同一性の拡張解釈に溢れているということにも気づかされますね。また、ジブリアニメの『千と千尋の神隠し』(2001年)に見るように、個体の識別と「名前」とは深い関係にあることも気づかされます。
転生や多重世界における個体の二重性を考え出すと、あらゆる根源的な属性すらそっくり入れ替わってしまうわけで、そこで同一性を維持しているのは「私は私」という自我の同一性・連続性しかない、ということになるのかもしれません。「私」の問題は後ほどまた考えます。いずれにしても、「人格」における同一性、個体性は、フィクションの中であらゆる属性をはぎ取られ、限りなく抽象的な「点」のようなものになっていくこともあるのだということを認識しておきたいと思います。
 |
登場人物の3分類 |
ここで、「〈役割語〉トークライブ!」第10回で触れた、フィクションの構造とキャラクターとの関係について考えてみたいと思います。第10回では、フィクションに現れるキャラクターを次のような3種類に分類しました。
| クラス1: | 〈ヒーロー〉すなわち主人公または主人公クラスのキャラクターで、言語的には、標準語を話すことが最も多い。それは、読者や視聴者にとって、一番接近しやすく、自己同一化しやすいという条件から来る制約である。 |
|---|---|
| クラス2: | 〈メンター〉〈影〉〈変貌者〉〈トリックスター〉など、個性が強く、〈ヒーロー〉に良くも悪くも強い影響を与えるキャラクターが含まれる。言語的には、標準語やステレオタイプな役割語も用いられるが、独自のスタイル(キャラクター言語)で読者に強い印象を与える工夫がなされることも多い。 |
| クラス3: | いわば “その他大勢” のモブキャラで、名前も付けられていないようなその場限りのキャラクターを典型とする。言語的には、標準語も含め、できるだけシーンの中で目立たないスタイルを選ぶということが重要で、そういう意味では最もステレオタイプな役割語を用いるのはこのクラスである。 |
フィクションにおけるキャラクターの問題を考えるために、ここで「視点」について考えておきたいと思います。本多(2005:p. 32)は、「見る」行為が次の5つから構成される複合体であると述べています(古賀 2018 も参照)。
| (i) | 見る主体: | 誰が見るのか | (視点人物) |
|---|---|---|---|
| (ii) | 見られる客体: | どこを見るのか | (注視点) |
| (iii) | 見る場所: | どこから見るのか | (視座) |
| (iv) | 見える範囲: | どこからどこまでが見えるのか | (視野) |
| (v) | 見える様子: | その結果どのように見えるのか | (見え) |
フィクションで重要なのは、むろん「視点人物」です。すなわち、主人公、あるいはそれに類する重要人物は、多くの場合、その人物を通して物語が語られるところの視点人物であるからです。クラス1 のキャラクターとは、この視点人物と基本的に重なると見てよいでしょう。つまり、私たちはクラス1 の人物の目を通して物語世界を見ます。つまり、クラス1 の人物は、物語を享受する “私” という個体と重ね合わされています。このクラスの人物の役割は、“見る” ことが中心なので、自分自身がどのように “見える” のかは実は必ずしも重要ではない場合も多くありますし、むしろ色濃い特徴がない方がいい、とも言えます。この特徴を言語的に端的に表すのが “標準語” であり、「主人公は標準語を使う」という “役割語セオリー” はここから出てきます。“見える” 特徴、つまりキャラクターの属性は、人格の個体性・唯一性に付随して与えられる、二次的なものです。
これに対し、クラス2 は、物語を賑わわせる、個性豊かな脇役群であり、さまざまに意匠を凝らした属性が与えられることになります。ステレオタイプな役割語も用いられますが、役割語をずらしたり混ぜ合わせたり、あるいは従来にはなかった奇妙な言葉づかいが与えられることもあるでしょう。例えば、「〈役割語〉トークライブ!」第7回で登場した〈ボクっ子〉は、かわいい女子の見た目と男の子的な話し方という、一見矛盾する属性が同居させられている例です。村上春樹作品に登場する「ナカタさん」(『海辺のカフカ』)や「ふかえり」(『1Q84』)や「騎士団長」(『騎士団長殺し』)の話し方などは、ユニークなスピーチスタイルの代表例とも言えます。
このように、個性豊かな属性が与えられるのは、視点人物である主人公から “見られる客体”=「注視点」の人物であるから、とも言えます。しかし一方で、単に属性だけでそこに実在性が感じられないキャラクターは、読者に強い印象を与えないというのも事実です。つまり、属性の背後に確たる “人格” を感じさせることで、より強いキャラクターが創造できます。“キャラを立てる”(宮本 2003)ということの一面は、そのような “人格” の確立であり、場合によってはクラス2 の人物を視点人物に取り立てて、サイドストーリーを語らせることもあるのです。「〈役割語〉トークライブ!」第6回で採り上げられた「ツンデレ」キャラクターは、まさに「ツンツン」キャラと「デレデレ」キャラが一つの人格に混然と混じり合っているキャラクターであり、それ故に強い存在感の輝きが放たれるとも言えます。また、村上春樹の『1Q84』BOOK 3 では、それまで脇役であった「牛河」が視点人物として躍り出てきたりします。
クラス3 の登場人物は、これに対し、“見え” ている範囲の属性がすべてであり、その奥にある人格を感じさせる必要はありません。むしろ、人格が見えるような強いキャラクターにしてしまうと、伏線として最後に回収しない限り、物語の構造を壊してしまうとさえ言えます(清水 2000;金水 2003:第2章も参照)。
 |
おわりに |
最終回である今回は、キャラクターの「同一性」「個体性」(固有性・唯一性)という概念に則って、改めてキャラクターとは何か、役割語とは何か、という問題を振り返ってみました。フィクションとキャラクターは、人間存在と我々の経験に根ざし、社会、歴史、文化、宗教等、人の営みのあらゆる面と関連する概念であるということを感じていただければ幸いです。
ご感想、ご質問等ありましたらぜひ nihongo@kenkyusha.co.jp までお寄せください!
| (by 石橋博士) |
またどこかで会おう。 |
〈参考文献〉
|
金水 敏(きんすい さとし) 1956年生まれ。博士(文学)。大阪大学大学院文学研究科教授。大阪女子大学文芸学部講師、神戸大学文学部助教授等を経て、2001年より現職。主な専門は日本語文法の歴史および役割語(言語のステレオタイプ)の研究。主な編著書として、『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』(岩波書店、2003)、『日本語存在表現の歴史』(ひつじ書房、2006)、『役割語研究の地平』(くろしお出版、2007)、『役割語研究の展開』(くろしお出版、2011)、『ドラマ方言の新しい関係―『カーネーション』から『八重の桜』、そして『あまちゃん』へ―』(田中ゆかり・岡室美奈子と共編、笠間書院、2014)、『コレモ日本語アルカ?―異人のことばが生まれるとき―』(岩波書店、2014)、『〈役割語〉小辞典』(研究社、2014)などがある。 |
|
関連書籍 |
|
複写について|
プライバシーポリシー|
お問い合わせ
Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |